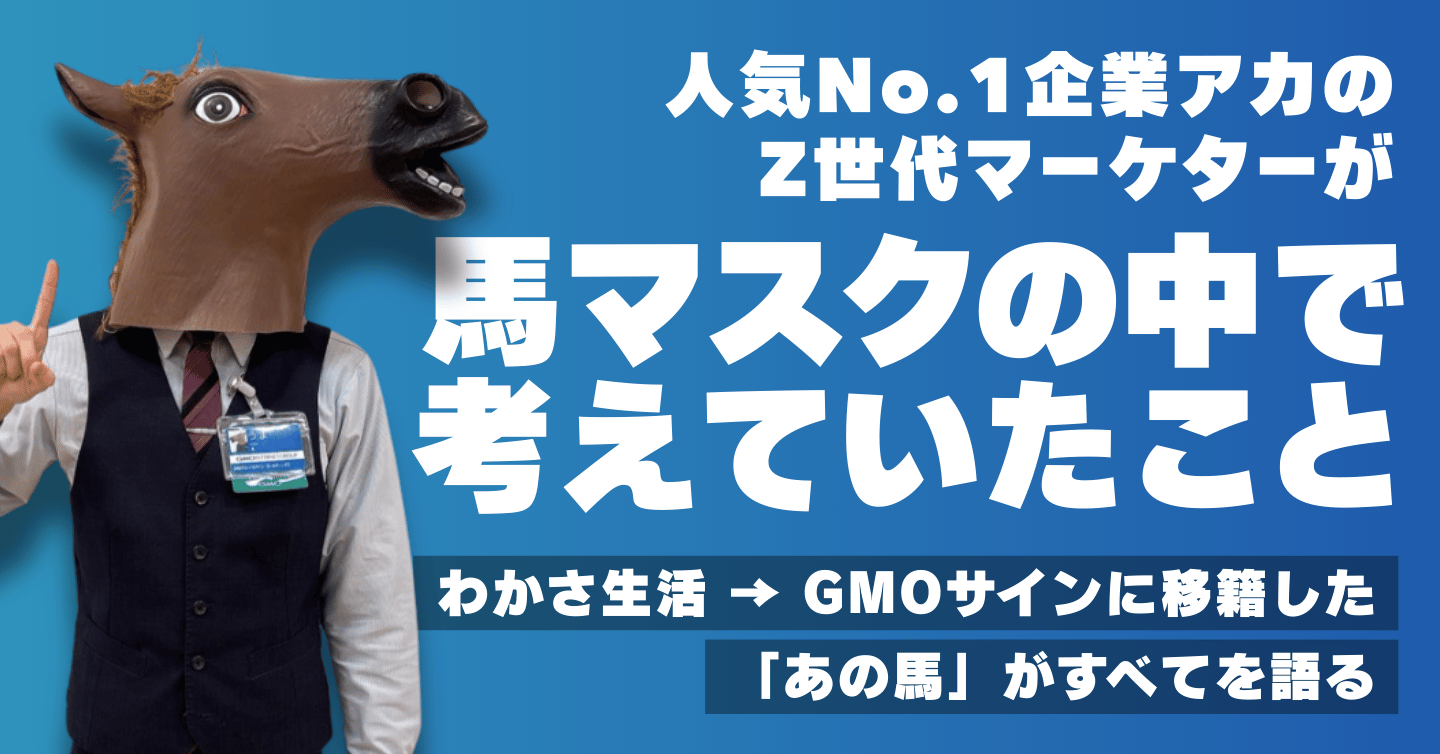知らない場所へ一人で出かけるとき、私たちは無意識に地図アプリを開き、周囲の景色を確認しながら歩いています。しかし、視覚に障害がある方にとって、単独での歩行は時に“命に関わる行為”になり得ます。
株式会社Ashiraseが開発した歩行ナビゲーションデバイス「あしらせ」は、靴に装着した振動ベルトが進行方向を足元に伝えることで、安全な歩行を支援するプロダクト。その特徴は、音声でも画面でもなく「足元から伝える」という点にあります。
元Hondaのエンジニアである代表・千野歩氏は、なぜこの難しい領域に挑み続けているのでしょうか。全台回収や発売延期といった厳しい判断を経てもなお、同社が前に進み続ける理由には、「ユーザーの人生に責任を持つ」という一貫した軸がありました。
あしらせ公式サイト
自動車技術を「歩く」支援へ。Ashirase誕生の原点

――Ashiraseは、どのようなビジョンを掲げている会社なのでしょうか。
千野氏:私たちは「歩く」という、人の根幹となる能力にフォーカスしています。そして、歩くことには思っている以上の課題を抱えている方がいらっしゃいます。テクノロジーでそこを少し支えるだけで生活の豊かさが大きく変わるんです。現在は視覚障害者向けの歩行ナビゲーションを提供していますが、単なる道案内ではなく、「自分で歩ける」という体験そのものを支援したいと考えています。
――もともとHondaで自動運転などを手がけていた千野さんが、「歩行」に着目された背景はどのようなものでしょうか。
千野氏:身内の事故がきっかけでした。自動車分野では安全技術が進んでいる一方で、人が一人で歩いているときにも、外的要因がなく命を落としてしまうケースがあるという事実に衝撃を受けました。
「モビリティ」という視点で見れば、歩行も移動の一つです。自動車で培った技術や考え方を、歩行支援に応用できないかというところから、「あしらせ」の構想がはじまりました。
なぜ「足元」だったのか。最も地味で、最も難しい選択

――歩行をサポートするためのデバイスとしては音声や骨伝導など選択肢がある中で、なぜ足元の振動を選ばれたのでしょうか。
千野氏:実は、最初から「足」に決めていたわけではないんです。白杖に振動をつける案や、腰回りに装着する案など、さまざまな選択肢を検討しました。
ただ、当事者の方から「杖は私たちの目なんです」と言われたことが、大きな転機でした。視覚障害者にとって、聴覚と手で得る情報は安全に直結します。そこを邪魔するインターフェースは、どんなに高機能でも使えないと判断しました。
音声でサポートする案も検討しましたが、音声は最初から最後まで意識を向けないと理解できないインターフェースです。たとえば「50メートル先を左に曲がる」という指示でも、少なくとも5秒はじっと聞いていないといけません。歩行中に常に音声へ注意を向けるのは、かえって危険になる場合もあるので、必要なときに直感的に受け取れる振動に着目しました。
体のどこが一番適しているかを生理学的に検証したところ、顔や手の次に振動を感じ取りやすいのが「足の甲」でした。ただし決め手は生理学だけではなく、「生活の中で管理しやすいか」という視点です。腰回りは最後まで残った案でしたが、ご自宅の中での着脱を考えた際、靴に付けるデバイスであれば必ず玄関で行うということに気付き、使われ続けるための条件を積み上げた結果、足元に行き着きました。
この選択は、技術的にも事業的にもリスクの高い判断でしたが、創業前に500〜600人規模の視覚障害者に検証を重ね、「これなら安心して使ってもらえる」という確信を得られました。
「やる場所」より「やる意味」を大切にした
――「あしらせ」はHonda発のプロジェクトでしたが、千野さんは独立を選ばれました。これにはどのような理由があったのでしょうか。
千野氏:一緒に取り組むメンバーに社外の人が多かったこともあり、そもそも社内で完結させる発想は強くありませんでした。それ以上に「早く社会実装して、実際の生活で使われるものにしたい」という思いが強かったんです。
どこでやるかより、どう価値を届けるか。その実現に一番近い形を選んだ結果が、独立でした。
――迷いはなかったのでしょうか。
千野氏:よく聞かれますが、正直あまり迷いませんでした。当時35歳で、家族もいましたが、妻も応援してくれましたし、何より当事者の方々からの期待が大きかった。「やらない理由」を考える余地がなかったというのが正直なところです。
「この判断で会社が終わるかもしれない」と感じた全台回収と発売延期
――「あしらせ」は購買型のクラウドファンディングで販売された直後、全台回収という大きな決断をされています。
千野氏:一部で振動しなくなる故障が単発的に発生しました。歩行を支援する製品で、信頼性に問題がある状態は許されません。スタートアップとしては非常に厳しい判断でしたが、全台回収せざるを得ませんでした。
――経営的な不安はありませんでしたか。
千野氏:正直、資金面も含めて相当厳しかったです。この判断で会社が立ち行かなくなる可能性も考えました。ただ、ここで目をつぶって、ユーザーの人生に取り返しのつかない影響を与えてしまうということだけは避けたかったんです。
結果的に、問題の本質はハードウェアだけでなく、オンボーディング不足にもあると分かりました。体験会では説明しながら使ってもらえても、一人で箱を開け、設定し、使いこなすまでの壁を想像しきれていなかったのです。販売当初は訪問サポートもするなど、体制を整えてから再始動したかたちです。
「行ける場所」ではなく「取り戻した日常」にあった本当の価値

――ユーザーからの声はたくさんお伺いされているかと思いますが、特に印象に残っているものはありますか。
千野氏:本当にたくさんあるので一つに絞るのは難しいのですが、印象的だったのは中途失明された女性のお話です。
それまで外出や家事の多くをご主人に頼っていて、申し訳なさを感じていたそうですが、「あしらせ」で最初に登録したのは自宅からゴミ捨て場までのルートだったそうです。
「Siri、ゴミ捨て場までナビして」と声をかけるだけで、自分ひとりでゴミ捨てに行けるようになり、「これが私の仕事になった」と話してくれました。その言葉が、とても心に残っています。
――新しい場所に行けるようになる以上に、大きな意味があったということですね。
千野氏:そうですね。私たち自身も最初は「行ったことのない場所に行けるようになる」価値を想定していました。でも実際には、これまで当たり前にできなかった日常の行動を取り戻せることのほうが、はるかに大きな意味を持っていたんです。
「できなかったことが、できるようになる」。その積み重ねが、自信や尊厳につながっていくのだと、ユーザーの方々から教えてもらいました。
足元から広げる「歩ける場所」。屋内ナビの先に見据える世界
――現在はどのような課題に向き合われているのでしょうか。
千野氏:利用者の方からは、地下通路や駅、ショッピングセンター、病院など、日常的に訪れる屋内での歩行に課題があると多く聞いています。屋内はGPSが使えず、地図データも不足しているため、施設内を撮影させていただいたり、フロアマップの情報を提供してもらったりと、施設側の協力が不可欠です。
正直、時間も手間もかかりますし、すぐにスケールする話ではありません。それでも、日常で一番困っている場所から解決しなければ意味がない。ひとつずつ「歩ける場所」を広げていくことで、結果的に視覚障害者の方の選択肢も広がる循環をつくりたいと考えています。
また、世界中にいる視覚障害者の方々にも「あしらせ」を届けたいです。現在、3億人以上の方が視覚障害を持っていると言われていますが、その多くは新興国に集中しています。新興国では医療を十分に受けられないことが原因で視覚障害を併発するケースも少なくありません。
屋内ナビなど、日本で積み重ねてきた知見は、そのまま世界でも通用すると感じています。日本で磨いた技術を、世界中の課題解決に活かしていきたいですね。
自分の価値観に嘘をつかない

――最後に、何かに挑戦しようとしている人へメッセージをお願いします。
千野氏:私はチャレンジすること自体が正解だとは思っていません。大切なのは、自分が何を大事にしているか。そこに嘘をつかないことです。
本当に解決したい課題があるなら、やらないことの方がリスクになる。自分の気持ちに正直に、一歩踏み出し続ければ、必ず共鳴してくれる仲間が現れると思います。あなたの挑戦が、誰かの「できる」を増やすきっかけになることを願っています。