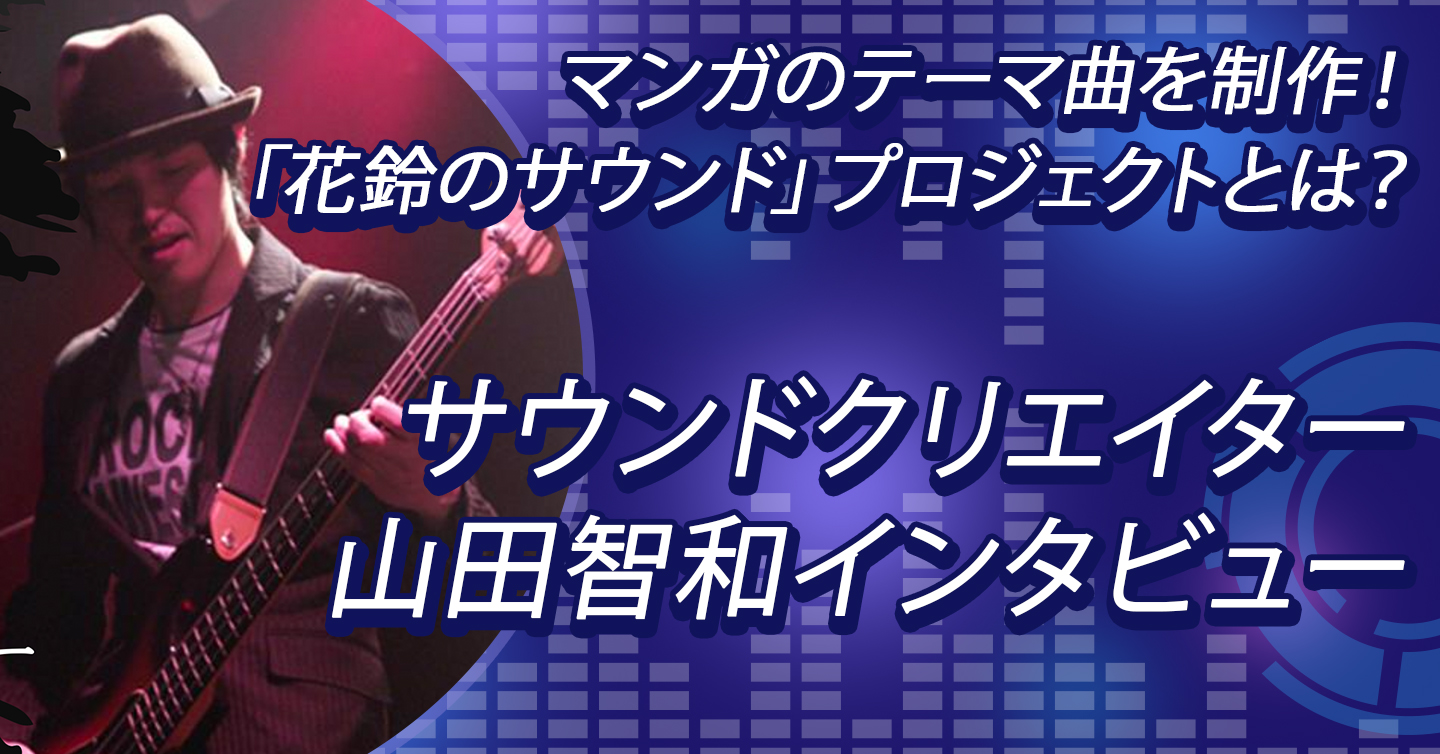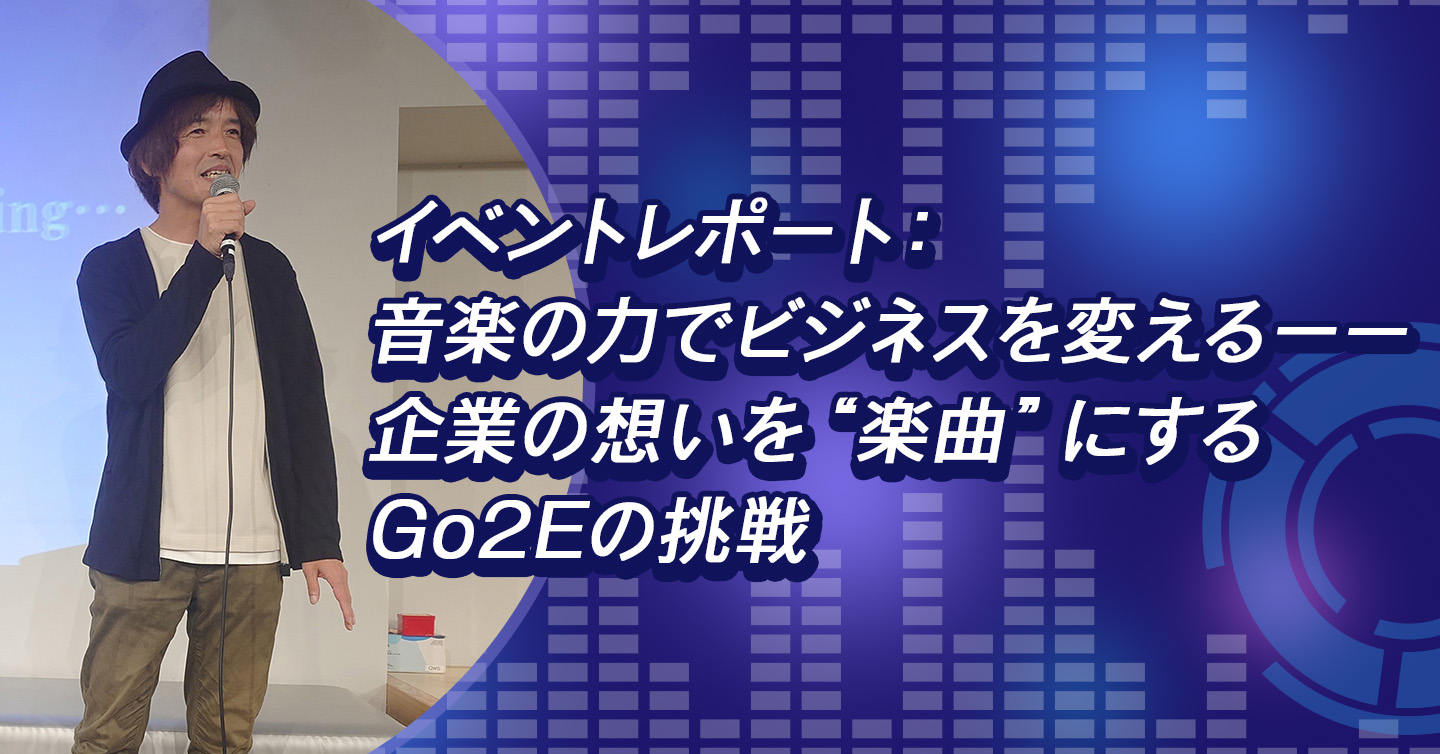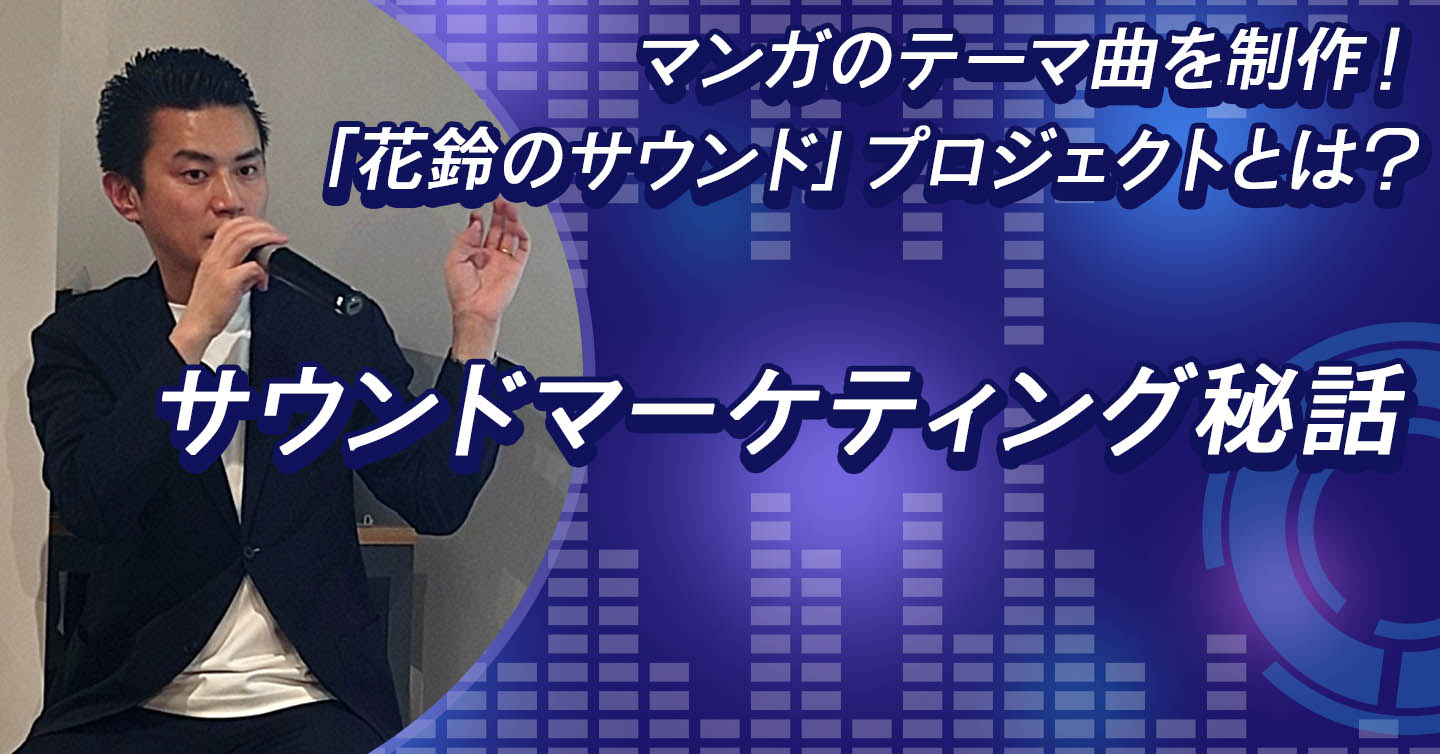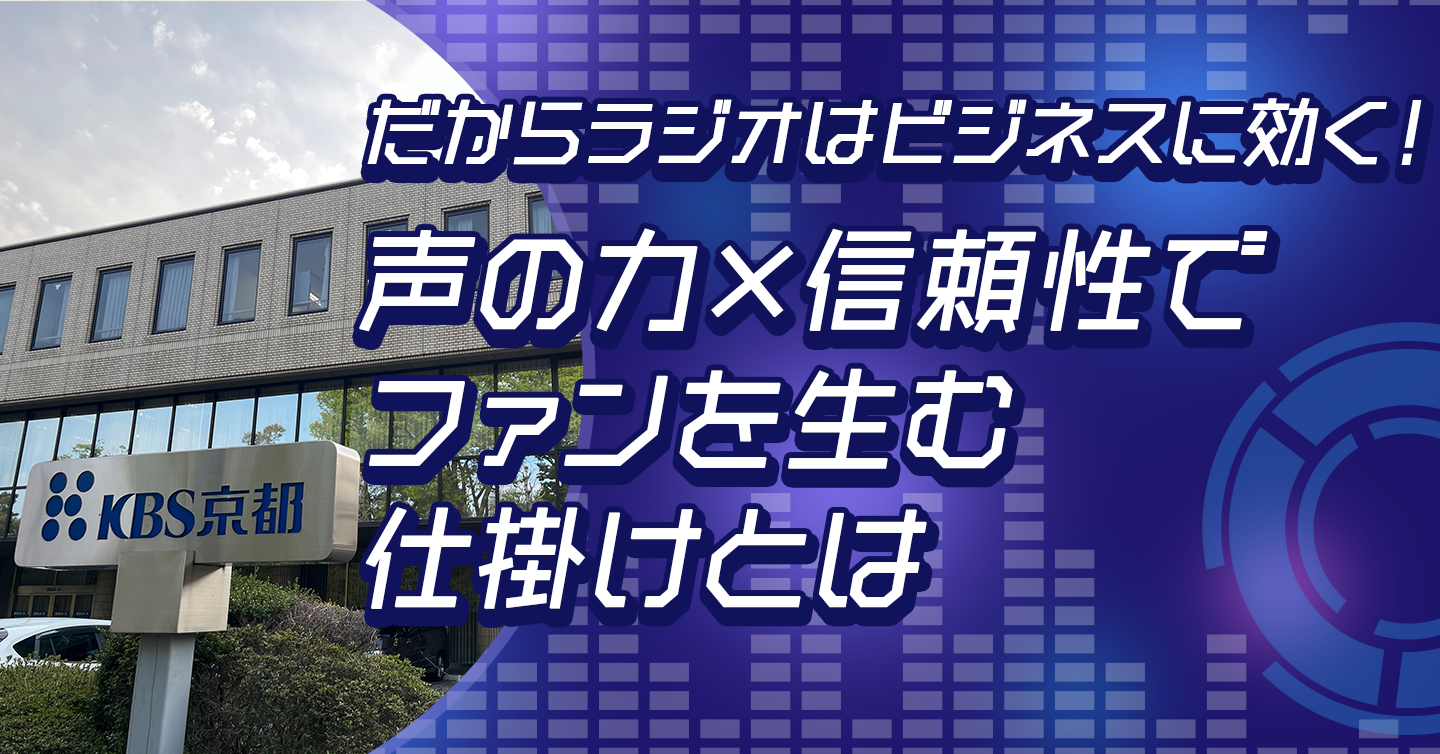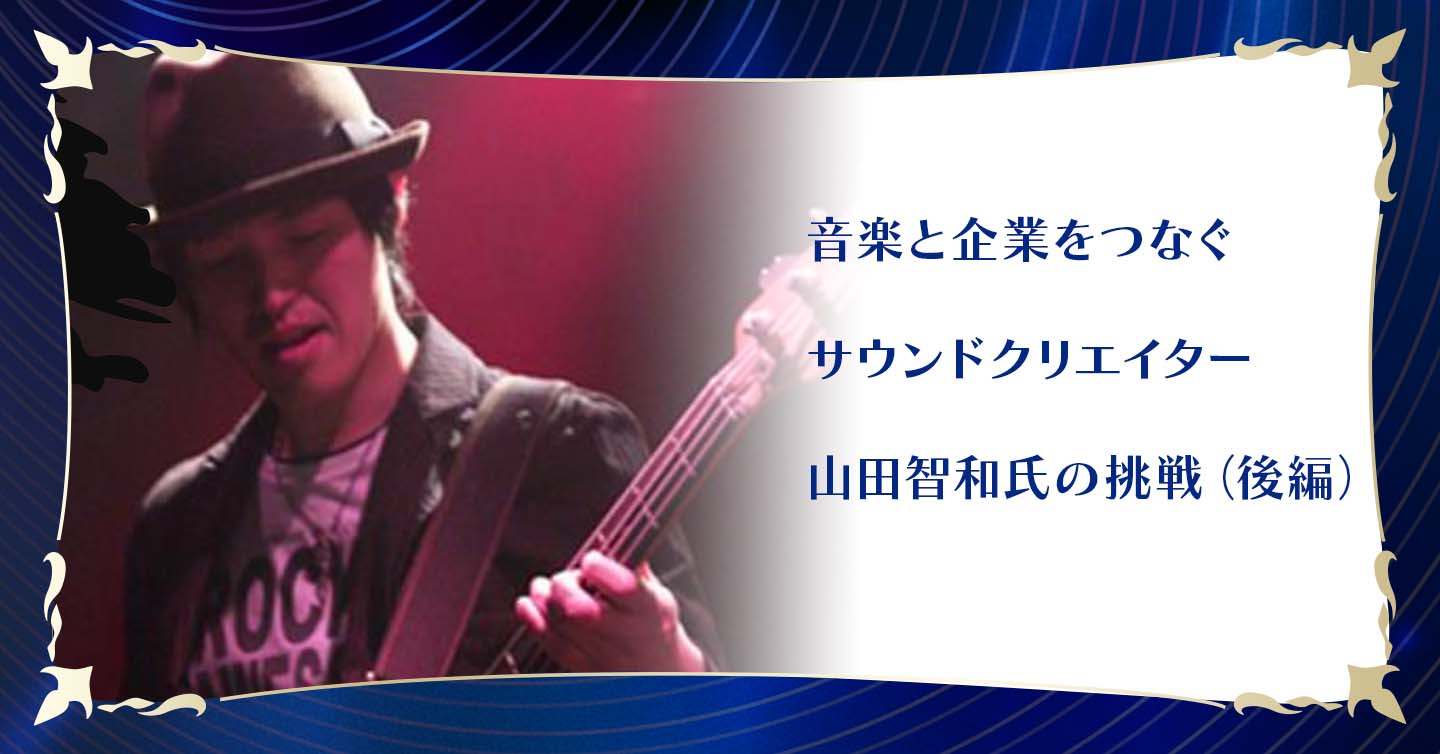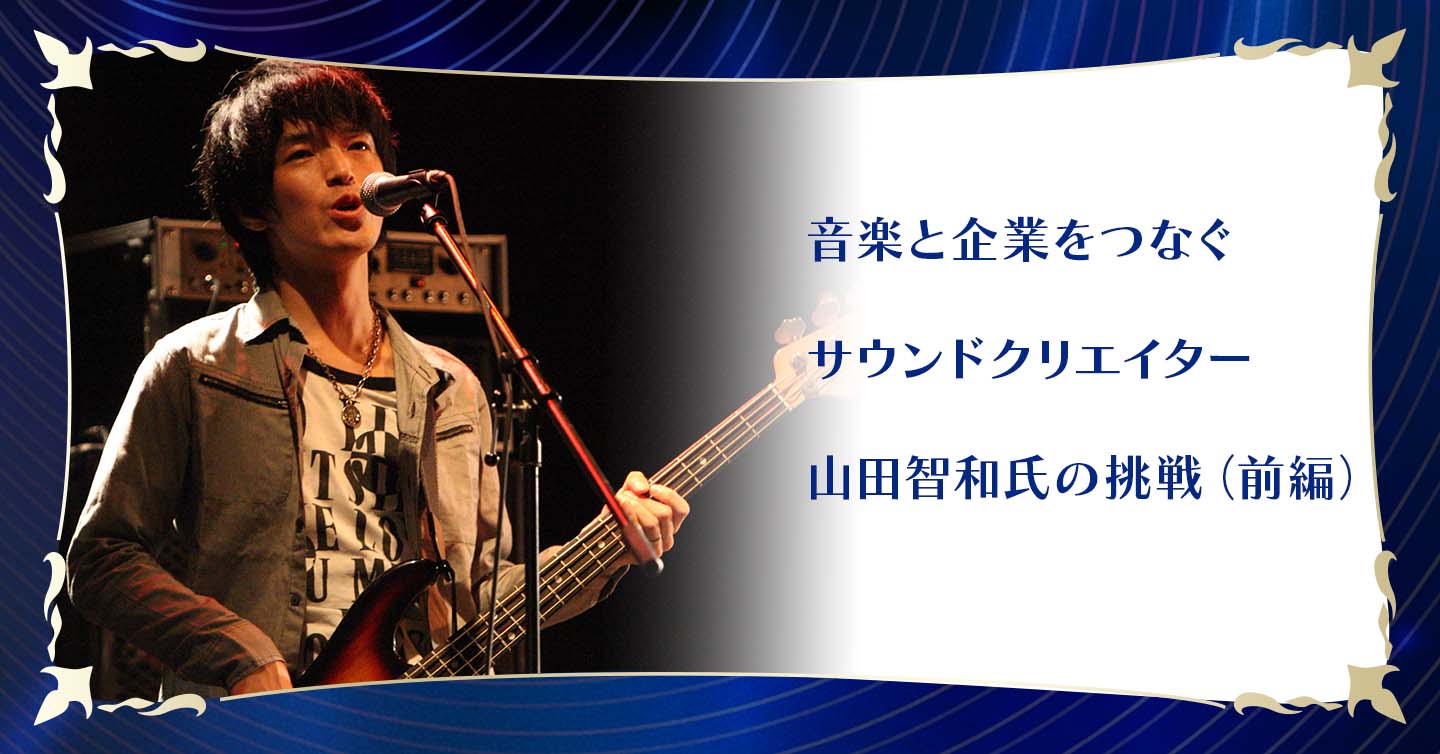甲子園を目指す「高校球女」を描く青春マンガ『花鈴のマウンド』。本作を音楽で広げようというプロジェクト「花鈴のサウンド」が立ち上がりました。このプロジェクトから生まれた『花鈴のマウンド』テーマ・ソング「希望のFLAG」はSNSでも大反響。アニメならぬ「マンガ」の音楽を作るという、この大胆な試みはどのようにして生まれたのでしょうか?
「希望のFLAG」を手掛けた作曲家にして、株式会社Go2E代表取締役として「“音“が持つ可能性で、ビジネスを変える」ことに挑んでいる山田智和氏が「花鈴のサウンド」プロジェクトについて語るロング・インタビューをお届けします。
山田氏に音楽家としてのキャリアから音楽とビジネスを繋ぐ可能性についてまで伺った記事も併せてご覧ください!
・音楽と企業をつなぐサウンドクリエイター・山田智和氏の挑戦(前編)
・音楽と企業をつなぐサウンドクリエイター・山田智和氏の挑戦(後編)
この楽曲、動画が生まれた背景とは?
よろしくお願いいたします。
山田さんが制作した「希望のFLAG」は、TikTokで34万再生、5万いいねを超えていました。(2025年6月20日時点)
楽曲単体で捉えてもいい曲だと感じたんですが、この楽曲はどのように生まれたんですか。
僕は高知県の香川出身なんですけども、とあるライヴイベントに招待していただいた時に、同じ高知出身の出版社の方がいらしてるということで、イベントの主催の方が紹介してくださったんです。
その出会いが、「希望のFLAG」が生まれたまさにスタート地点になります。
どういった流れでそのイベントに参加することに?
イベント主催の方とは、もう10年以上、連絡を取ってなかったんですよ。
その時は、以前のインタビューでもお話しした、自分が作曲家事務所の会社を引き継いだタイミングでもあって。
「とにかくいろんな人に相談してみよう」ということで、「どうしよっかな……今回連絡してみようかな……」って思って電話帳を開いたときに、間違って電話をかけちゃったんです。
間違って!?
そうなんです(笑)。指があたって電話がかかっちゃって(笑)。
「やばい!」と思って切ったんですけど、折り返しがきちゃったんです。
それで「ちょっと会社を引き継いだんです」って話をして。
「何かできることないですかね」と相談をしたら、「イベントを立ち上げて主催しているから、一度おいでよ」と誘われて。
そして、さっきお話しした出会いに偶然繋がったんです。
出版社の人と出会って、どんな話をしたんですか?
彼も学生時代、僕の出身地である香川に住んでいたということで。
それも自分の実家とすごく近いところにいらっしゃったことが判明して、一気に親近感を感じました。
さらにアニメがお好きということで、自分がアニメ関連の楽曲を手がけてきたことに関してもすごく理解してくださって。
そういう「ご縁」とか「タイミング」をめちゃくちゃ信じているところがあるので、「これは何かあるかもしれない」と思ったんです、直感的に。
それで、もっとお話ししたいなと思ったんですよね。「これっきりにはしたくないな」っていう。
そう思っていたら、その出版社の方からも「ちょっとこの後いいですか」と言っていただいて。
すごい出会いですね。
カフェに行って、出版社の方といろいろとお話しするなかで、株式会社わかさ生活の社長のことと、その社長がマンガ好きで、自分でシナリオを書いて『花鈴のマウンド』という作品まで作ってしまったという話を伺いました。
その社長が携わるいろんな取り組みについても聞いた時に、自分が会社を引き継ぐにあたって「こんな経営者になりたい」とまさに思い描いていた経営者像を体現している方だと感じたんです。
そういう方が手掛ける取り組みに関して、自分の仕事である音楽で何か協力できるのであれば喜んでやらせていただきたい、と。
そういうことで、『花鈴のマウンド』のプロジェクトに携わることについて、もう最初から答えは「イエス」と決まっていました。「絶対やります」という(笑)。
「こうなりたいと思っていた経営者像」とは、どんなものだったんですか?
とにかく「他己主義」でいられる方という部分でした。
「自分がお金を儲けたい」というものではなく……お金はもちろん大事なことだと思うんですけど、それを「どこかに還元していく」という……。
「自分ファースト」ではなくて、「誰かに還元するためにお金を稼いでる」というか。そういう経営者になりたいなと思って。
「そのために、どんな価値提供できるだろうか」みたいなことを常に考えて動かれている方で。そういうあり方に憧れがあったので。
なるほど。
さらにマンガの原作まで手掛けている(笑)。
こんな人になりたいな、と思って。
だって面白いじゃないですか!
「こういう経営者になりたい」と思っていたような方がいて。
「クリエイティヴ」でもあるなんて(笑)。
これが、例えばすごく立派な会社の社長が「自分がなりたい像だ!」と感じたとしても、すごいなとは思うけど、自分と接点が少ない。
でも、そんな方が「クリエイティヴ」でもあったんです。
これは、サポートできる何かが絶対にある、と。
その後、マンガを全部読ませてもらって、作曲を始めました。
曲の生まれ方、作り方
作曲って、どのような流れで曲が生まれていくんですか?
やっぱり、まず「リズム」ですよね。
野球と言えば、応援におけるあの独特の「タン、タン、タンタンタン」っていうリズムがある。やっぱり、そのリズムっていうのは絶対に活かしたいな、曲の中に反映させたいな、っていうところからでした。
そうすると「リズム」がまず先にできて、「こういうリズムの曲を作っていきたい」となる。
なるほど……モチーフから、まず「リズム」を作るんですね。
そうです、はい。リズムから作ることって多いんですよ。
まず「リズム」、そして「テンポ」、そこから「メロディー」を考え出すとか。
作り方にはいろんな順番があるんですけど、この曲に関しては「リズム」から決めましたね。
「メロディー」を考え出すというところなんですが、なんと表現するのが正しいのか……「考える」んですか? 「降りてくる」んですか? 「浮かんでくる」んですか?
「今回はこういうリズムで行きたい」っていうところから始まって、そのリズムを流しながら、それに合わせてギターを弾いてメロディーを作っていく、という感じです。
何パターンかのメロディーを試すんですけど、だいたい1つ目に降りてくるものが一番良かったりするんですよ(笑)。
「結局、これだよな」という。
ファーストインプレッションがすごく大事です。
その「メロディーができるまで」って、どれくらいのお時間がかかるものなんですか?
「モノによる」としか言えないのですが(笑)。
30年以上、人より音楽を聴いて、人より音楽を考えながら作り続けてきたので、頭の中、指先に「音楽の回路」があるような感じなんです。体が覚えているというか。
歌詞に込めた”技巧”
歌詞には、どのような想い、メッセージを込められたんですか?
最近は「カッコいいけど、歌うのが難しい」「一回じゃ歌詞が覚えられない」というテクニカルな曲も多いのですが、「希望のFLAG」の歌詞は「覚えやすさ」「歌いやすさ」「わかりやすさ」を徹底的に考えました。
作品のテーマが野球=「スポーツ」ですからね。
「そんな難しくしてどうする?」みたいな。
ただ「青春」というテーマにしていたら、何かいろんな表現があったかもしれないですけどね。
でも今回はやっぱり「スポーツ」なんだよな、と。
山田さんのそういう歌詞の発想は、どこから来ているんでしょうか。
14歳でベースを手に取って、音楽を始めたそうですが、それから、真面目に学問として勉強したような経験はないんですよね。
ないですね。
でも、今回に関して言えば、自分自身、いろんなスポーツをやってきたわけです。学生時代はテニスをやって。
そういう経験をもとに「スポーツをやっているときにどういう曲が刺さるかな」と考えたら、「ストレートに来てくれよ!」「頑張れって応援してくれよ!」「かっ飛ばせ!って言ってくれよ!」って(笑)。
そうして歌詞のベースができて、そこからプロの作詞家の人に聴いてもらって、見てもらって、一緒に歌詞を作っていきました。
専門の作詞家の人は「歌っていて、聞いていて気持ちがいい母音の繋がりかどうか?」という独自の目線を持ってもいて、協力をいただくとより良いものになっていくんです。
最後に作詞家の方にもお力を借りるんですね。
「モチーフ」から「リズム」が生まれ、ギターを手に取って「メロディー」が出てきて、歌詞を考える時は「スポーツをやってるなら、こうでしょ」とベースの言葉が生まれ、最後は作詞のプロが調整をする。
そうして『希望のFLAG』という曲が生まれたと。
ここまでのお話で十分に面白いのですが、例えばこの曲に「特別な工夫」があるとしたら、「ひと手間、加えた」部分はありますか?
この曲、実はサビで「転調」しているんですよね。
サビに行く前のところでヴォーカルが重なるんですけど、そこで実は転調している。
気づいてない方もひょっとしたらいるかもしれないけど、そうなんですよ。
ほほう、転調。それはどういう意図を込められているんでしょうか?
普通にサビに入ったら面白くないから、ちょっとしたスパイスは入れておきたい。
この曲自体はすごく「王道メロディー」ではあるんですけど、多少はやっぱり「おっ?」っていうフックは入れておきたい、ということで、そこで転調させました。
他にも「ここで転調を使ったら面白い」と思って作った曲とか、他の人が手掛けた曲でも「お、ここで転調入れてる、ニクイね」みたいな曲はありますか?
最近の曲はエグい転調をするんですよ。もうセオリーなんて度外視したような。
でも僕は、そういう転調は基本的にはやらないんですよね。
ちょっと専門的な話なんですけど、ストレートに行く平行調で進んで転調すると、「あれ? いま転調した? あれ?」みたいな自然な転調ができるんですよ。そういう転調の使い方が、自分としては割と好きなんです。
「何か変わった……?ようで変わって……ない? いや、変わってないようで、変わったよね?」みたいな感じで綺麗に転調するっていう。
わたしの作曲家デビュー曲である小野大輔さんの「雨音」でも、実は同じことをやっているんです。
デビュー曲から!?
その「転調」は、なぜ? いつから? 昔から使っていた技なんですか?
作曲を……やっぱり「仕事としての作曲家」になると、バンド時代にはなかった「制約」が生まれたんですよね。本当に色んな面で。
まず一番大きかったのは「キー」の問題です。
例えば声優さんの曲の場合、声優さんの「元々持ってる良い声」があって、たとえ「高いキーがすごい出る方」だとしても、音がそこまでいっちゃうと、もう「声優としての、その方の良い声のゾーン」じゃなくなったりしちゃうんですよね。
だから、「この声優さんの”良い声の部分”は、もうちょっと低い場所にある」とか、「こう話す声優さんの”喋り”の魅力を失わないように、キャラクター性を失わない音域で曲を作らないと」と考える。
そうすると、実は使える音域が狭いんですよ。
声優さんはもっと高いキーが出る、だけどそうすると別人になっちゃう、と。
だから、「この声優さんだと、ここがやっぱり”良い声のゾーン”なので、この狭い中で作ってください」となる。
その範囲だけで曲を作るのってすごく難しいんですよね。
「もうちょっと盛り上げるために、ちょっと高い音域に本当は行きたい」
「でも、音域をはみ出てしまうといけない」
そんな制約の中で試行錯誤している時に「平行調で転調する」と、いきたいメロディーはそのままで「調」だけ下げられたんですよ。
「制約」の中で生まれた技術、テクニックなんですね!
この転調を使うと、制約の中でも「行きたいメロディーに、ちゃんと行ける」ようになるんです。
「この声優の声、素材の魅力を変えたくないので、この制約でお願いします」というオーダーの中で、いろいろ試行錯誤して生まれたものですね。
作曲家の道に入ったけれど、まったく採用されなかった1年間の修業期間で生み出された技ですね、教えてもらったものじゃない。
やって、やって、やって……やってやってやってやってやってやってやって……
「……あれ? これ、こうしたら”調”が変えられるぞ?」といきついたものです。
素人質問で恐縮なのですが、山田さんは14歳から音楽を始めて、その”転調”のようなテクニックはどこかでしっかり学んだものなんですか? それとも自然と身に付けて、後から「あ、あれが転調っていうのか」という感覚なのですか?
「転調したらキーを下げられる」というのは知識というか、当たり前にやっていたことではありますね。
「ここで転調すると、全体のキーが下がるので、そうすると行きたいところに行ける」という。
だから、今流行りの急に脈絡もなく転調するようなことではないんですよ。
ちゃんと「ここに収めなきゃいけない」っていうか、オーダーに沿う形でまとめるという目的のための技術でもあります。
なんだか、ビジネスで言うところの「ピボット」みたいですね。
脈絡なく別のことを始める、別のところに行くという訳ではなくて、軸を持って、でも表現の幅を広げるために新しい場所に行くための技術が、山田さんの「転調」である、と。
そうですね。これが「自分のバンド」、「自分が表に立つアーティスト」だったら、まったく自分が好きなように転調したりするかもしれませんが、「人が表現したい世界観を曲で実現する”作曲家”」だから身に付いたものかもしれません。
わたしは主役ではないんです。
主役は、強い想いやビジョンを持った人たちであって、わたしは曲でそれをサポートしていくんだ、と考えています。
楽曲「希望のFLAG」を受け取った社長の反応
そのような意図や技巧を凝らして「希望のFLAG」という曲を作られたんですね。
「偶然の出会い」があって、「磨き上げられた技術」で曲が生まれた。
この曲を社長にプレゼンした時はどのような気持ちだったんですか?
「ワクワク」でしたよね。
「これから、この曲を聴いてもらうんだ」というワクワク。
しっかりとした経営者の方なんて滅多に会えない人なんでしょうが、なんでしょうね。
わたしは出会った数秒で「この人と、大体どういう感じになるか」というのが自分の中に沸くんです。「仲良くなれる人か、難しい人か」とか。
そういうのが立場とか関係なく、何となくスパッっとわかるんですよ。
社長はもちろんすごい方で、友達になれるようなレベルじゃないと思うんすけど、「あ、この方は友達になれそう」と思いました。
上とか下とか関係なく、友達になれそうだなって思ったんです。
今でも覚えているんですが、「希望のFLAG」を聴いていただく中で、社長のテンションがふっと上がる瞬間が、やっぱりありまして。
やっぱり自分の作品にわくわくしてくれるっていうのが一番嬉しいわけで。
それが、その瞬間が、一番嬉しかったですよね。
その純粋な気持ちが山田さんの原動力であり、作曲という世界で実績を残せる魅力、強みなんだろうなと思います。
その日は本当に盛り上がって、そのまま食事までご馳走になったんですよね。
そして「この曲を使って、大いにプロモーションをする」と仰ってくださった。
でも、そこから一つ、乗り越えないといけない壁があったんです。
壁?
曲を最終調整して完成させて納品したんですが、なかなか公開してくれなかったです。
次にお会いした時には、前回のニコニコ笑顔はなく神妙な顔をしておられました。
一瞬、曲がお気に召さなかったのかと不安になりました。
次の一言でその不安はなくなったのですが、それが”壁”でした。
「せっかくの曲をただ公開するだけじゃ勿体ない、マーケティングに繋げたい」
「あ、そこか」と思いました。
というと、他にも同じような壁を感じることがあったのでしょうか?
はい。
それまでも「曲をもらったけど使い道が分からないから、とりあえずYouTubeに上げている」という会社様や「社内で朝礼の時に流している」という会社様がいらっしゃったんです。
プロモーションが得意だったり、PRする方法を明確に持っていたりする方はガンガン曲を使っていただけるのですが、不慣れな方の場合は、いったん止まってしまうところでした。
最初は「これほどの会社の社長でも、そこで一回止まってしまうのか」と思ったのですが、逆に「これほどの会社の社長だから、使い道までちゃんと考えるのか」とも思いました。
そこの「壁」をちゃんと見せてくれた社長には、今改めて感謝しています。
そのおかげで動画の制作やSNSプロモーションまで一気通貫してやることの経験と楽しさをいただけました。
ということは、「希望のFLAG」の動画も山田さんが作られたのですか?
わたしが、ではなく「わたしの仲間が」です。
アニメ関係の知人の中に動画師と繋がりがある人がいて、その方にご協力をいただいて作った動画が今流れている「希望のFLAG」のMVなんです。
その方と出会ったのも偶然で、わたしが動画を作るなんて考えてもいなかった時に知り合ったんですが「なんだかこの人と仕事をしたいな、お任せしたいな」って思った方なんです。それも、やっぱり直感ですよね。
「偶然」と「直感」で生まれた曲であり、動画なんですね。「音楽」というクリエイティヴな世界でやってきている山田さんのその感覚は、他の人とは違うものがあるんだと思います。
動画がここまで伸びることも「直感」はありましたか?
いや、実は怖かったですよ。「このストレートな曲調がどれだけ効くだろうか?」と結構ドキドキする気持ちはめちゃめちゃありましたね。
ですが、結果として一定以上は受け売れられて嬉しいです。
今回のプロジェクトをすることで、なにか山田さんの中で変わったこと、新しく考え始めたことはありますか?
「音楽」だけだとできないことが、企業さんと一緒にやる事でできるようになる、ということですね。
音楽に自信がないわけじゃない。自分の作るものに対して自信はあるんですけど、もっと面白いことをして、社会的な価値を生み出すためには「音楽×●●」っていう、もう一つ必要だろうな、と考えていたのですが、それが形になっているような。
掛け算をすることで「音楽の力」も上がるし、「音楽と掛け合わせたものの力」もまた上がったりして、本当にシナジーが生まれるのになってずっと思ってはいたんです。
今回、やっぱり音楽と企業さんの想いがドッキングした時、それぞれの持っている力以上のものが出たんじゃないかな、という気はしていて。
音楽やMVだけだと、要は「エンタメの世界」なんですけど、そこに企業さんという「実生活で人々を支えている人たち」が重なることで、より多くの人が「音楽で生活が良くなる」ということが実現できる、という思いが強くなりました。
企業の人たちに「音楽はビジネスにも使えるものですよ」っていうハウツーのところを、自分自身がもっと試しながら、いろんな出口を創り出していきたいと、より強く思うようになりました。
そうすることで「わたしにとっての音楽そのものの価値」も、なにか新しいものになっていくように感じています。
「山田さんにとっての音楽そのものの価値」とは、どのようなものなのですか?
今までだったら、オーダーに沿った音楽を作って楽曲を提供して相手が喜んでくれて、採用されたらわたしも嬉しい。
でもあとは、その曲が売れようが売れまいが、私にはそこまで関係がないものだったんです。たくさん売れてくれればその分、印税が多くいただけるんで、それは大変ありがたいですけど、ただ「責任感」はないものだったんです。
ですが、企業の方に音楽を届けて使ってもらうって、こんなに責任が生まれるんだなっていうことをすごい実感しましたね。
今までは「良い曲を作っとけばいいでしょう」っていう考えがまだありましたが、それじゃ「まだ足りない」というか。
「その曲で、多くの人をもっと笑顔にしたい」と、これまで見えているようで見えていなかった「その先」を考えるようになりました。
「作曲家」から「作曲家 兼 経営者」になってから、山田さんの中で「音楽」の価値も変わっていったんですね。それって、「音楽性」にも変化を与えそうですか?
いえ、音楽性は変わらないと思います。
わたしは「作曲家」ですから、根っこの部分は「”これを伝えたい”と求められるものに対して、”音楽で再生産する”」というか……「音楽でも伝わるようにする」ということなので。それが作曲家……「職業作家」というものなんです。
「こういうことが伝わる曲にしたい、こんな雰囲気にしたい」という「クライアントさんの想い」が最初にあって、その中で音楽を作っていくっていうことなので、そこは変わらない。だから、音楽性も変わっていかないだろうなと思います。
わたしは元々「カメレオン作家」ですから、曲調の対応できる幅は多い自信もあります。そこがブレることはないな、とすごく感じています。
改めて、これからどんなことをしていきたい、どんな世界にしていきたいと考えられていますか?
とにかく、もっとたくさんの人に「音楽を使ってこんな楽しいことができるんだぜ!」、「音楽ってビジネスに使えるんだぜ!」と知ってほしいですね。それを示していきたい。いろんな人と出会いながら、どんどん作っていきたいです。
自分自身が14歳から30歳まで、バンドとしてメジャーデビューを目指していたけど、できなかった。夢を叶えられなかったという想いがあるので、企業さんとか起業家さん、そういう人たちの「メジャーデビュー」を自分の音楽でお手伝いができたら嬉しいなと思っています。
「音楽の力で、ビジネスを”メジャーデビュー”させるプロデューサー」みたいな存在になりたいですね。
「メジャーアーティストを、1曲の力でそれ以上売る」ことって音楽以外の力の要素も大きくて、わたしはその一部をお手伝いさせていただいているのですが。
今まだ知名度もなくて、それでも一生懸命頑張っている人を、その頑張りに音楽をちょっと付け加えることで、ひょっとしたら「メジャーデビュー」に辿り着けるかもしれない、っていう、わたし個人としての想いもあると思います。
「ビジネス界でメジャーデビューしたい企業」を、音楽で支える。
「全国デビューしたいと思っている地域」を、音楽で支える。
それが、今のわたしの夢、野望です。
そういうことが実現したら、最高にワクワクしますね。
山田さんが「その世界が実現した後、したいこと」ってありますか?
音楽の世界で頑張っているクリエイターを支えていきたいです。
これまで「歌唱力は、一流アーティストと変わらないけど、知名度がなくて歌で食べていけず、地元に帰った人」や「何十年も音楽をやっているけど、それじゃ食べられなくてアルバイトを続けている人」「何十曲、何百曲も曲を作っていて技術は一級品なのに、全然お金を貰えずに搾取されてる人」なんかをたくさん見てきました。
そんな人たちに、音楽を続けられる、音楽で食べていける環境を作ってあげたいと考えています。
音楽が「エンタメ」を超えて「ビジネス」の世界でも人を動かして、社会価値を生む。
音楽で喜ぶ人が増え、その結果として経済が回って、「作り手」も豊かになっていく。
わたしの人生を今の様なカタチにしてくれた、「音楽」というものへの恩返しでもある、とも考えています。
それも、わたしが実現したいことです。
本気で考えていらっしゃるということが、お話のされ方からヒシヒシと伝わってきました。
これからの山田さんの作る曲も、聴かせていただきます!
編集後記
偶然の出会いから生まれた「花鈴のサウンド」プロジェクト。
それは、マンガにテーマソングをつけるという斬新なチャレンジと、音楽をマーケティングに活用するというアイデアに展開し、制作した楽曲「希望のFLAG」がTikTokで広く拡散されるという成果に結実しました。
山田さんの言葉からは、「音楽×ビジネス」の大きな可能性が伺えます。そして、作曲家としての確かな技術とサウンド・マーケティングを追求する経営者としての責任感で音楽を紡ぐ真摯な姿勢も伝わってきました。
次回の「音の挑戦者たち」でも、引き続き「花鈴のサウンド」プロジェクトをフィーチャー。山田さんが「花鈴のサウンド」に携わるきっかけを作った編集者であり、山田さんと共に「音楽×ビジネス」の開拓に挑む志摩晃司さんの視点から、「花鈴のサウンド」に迫ります!