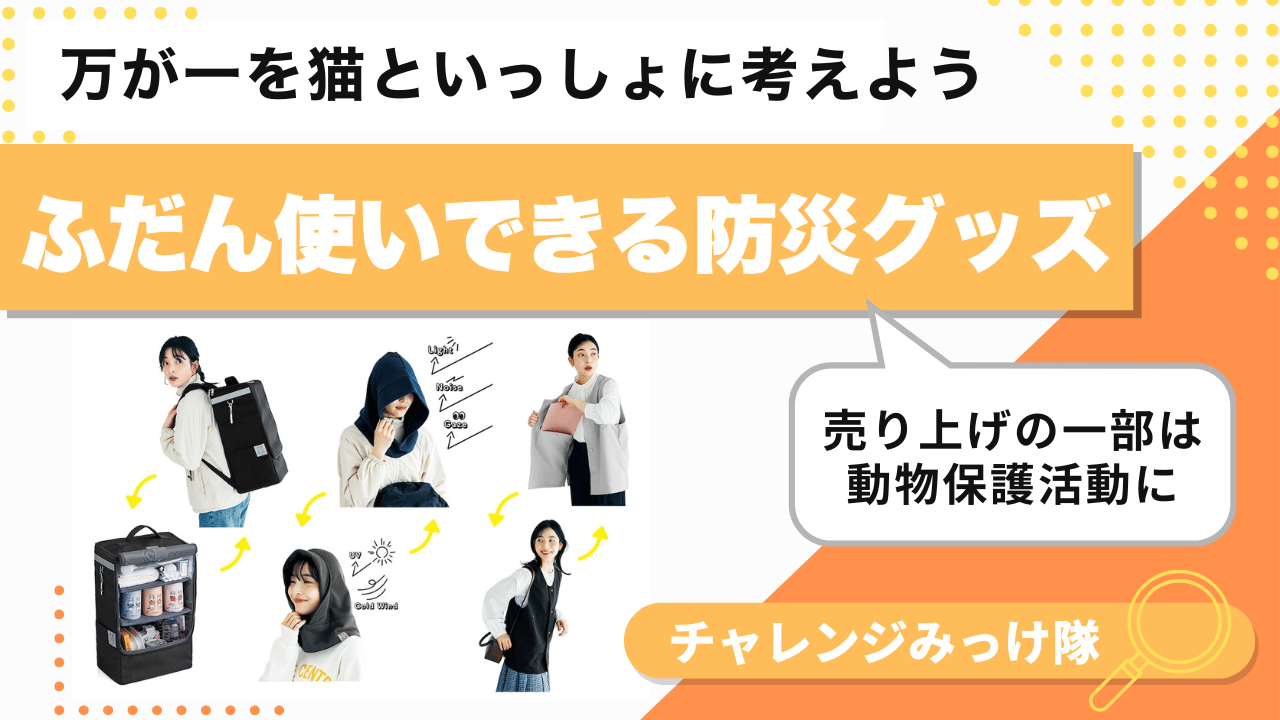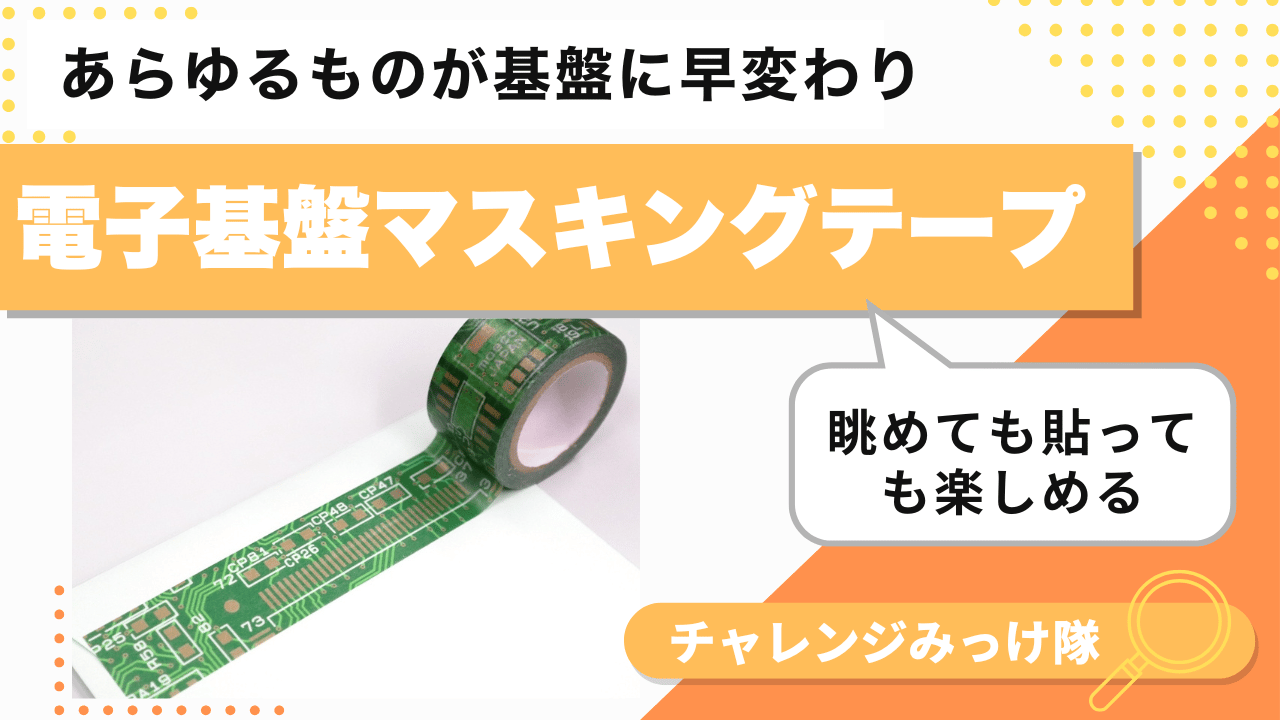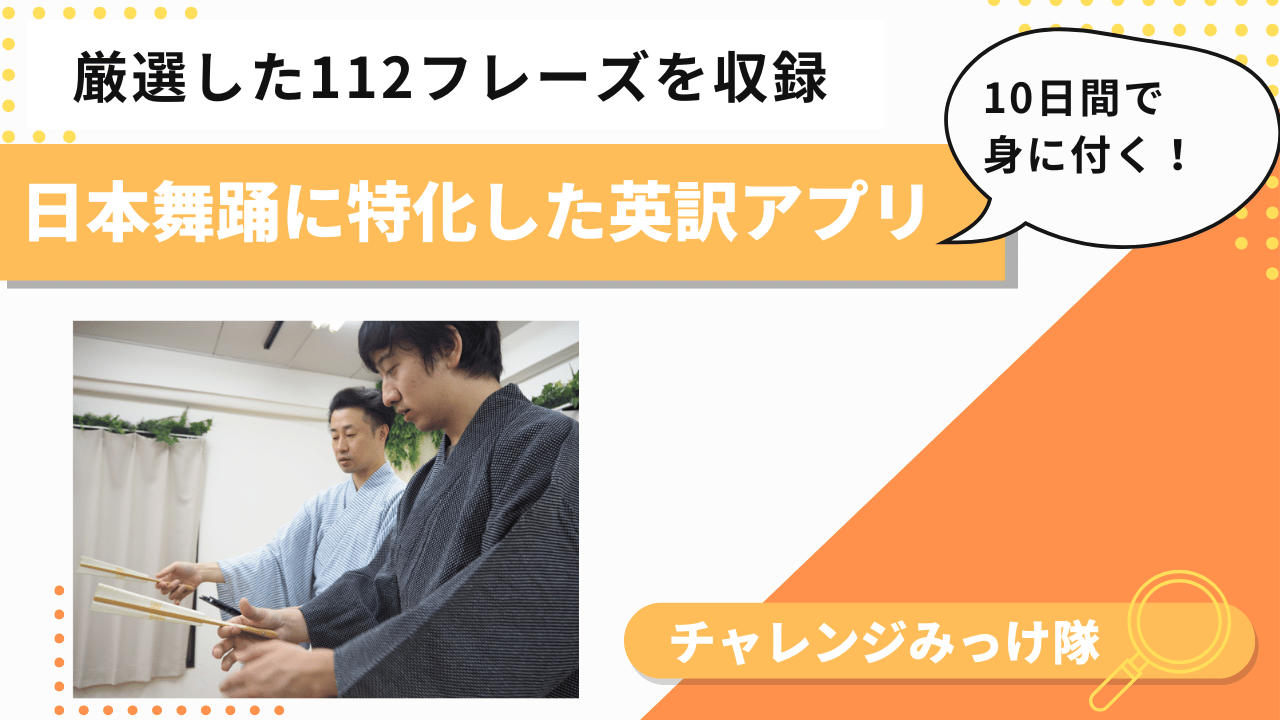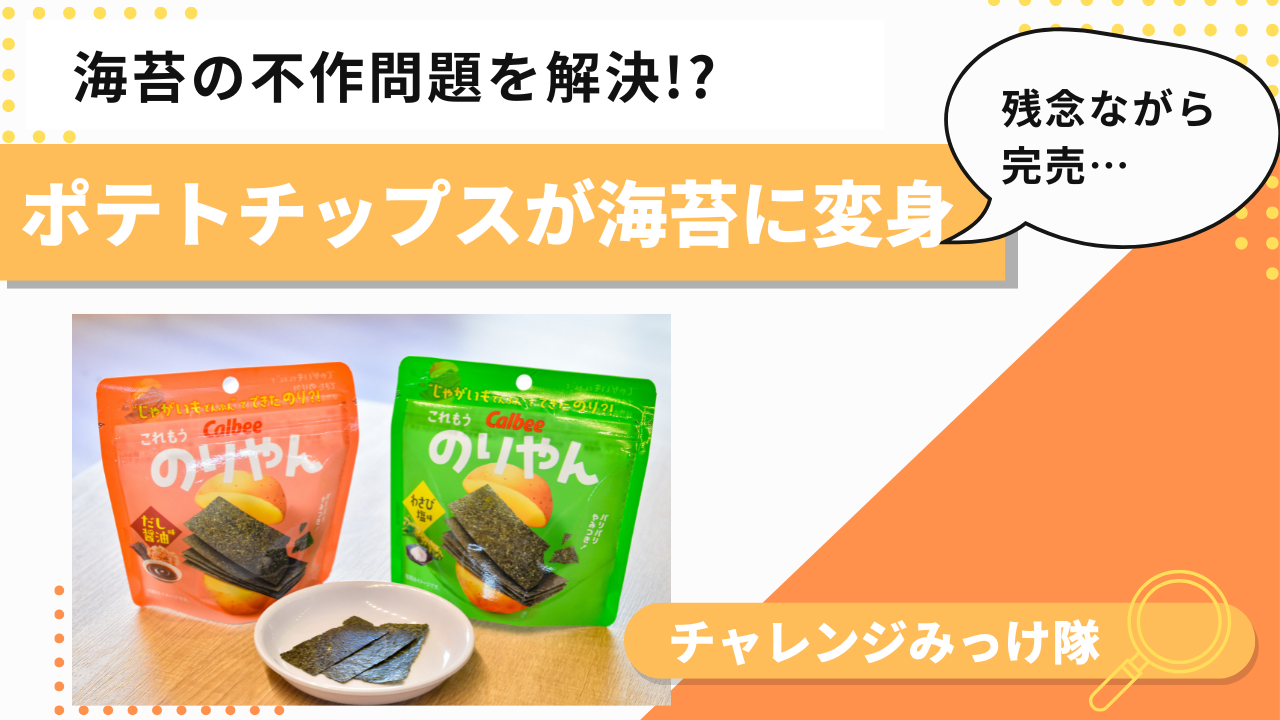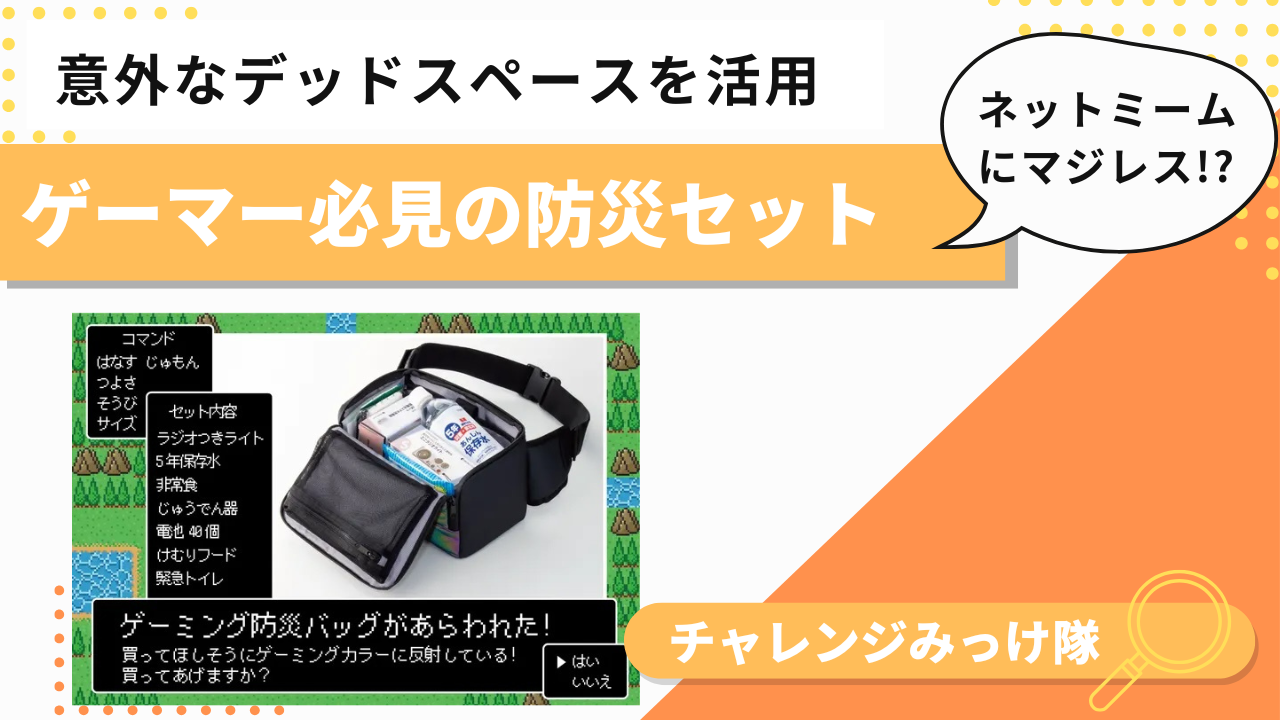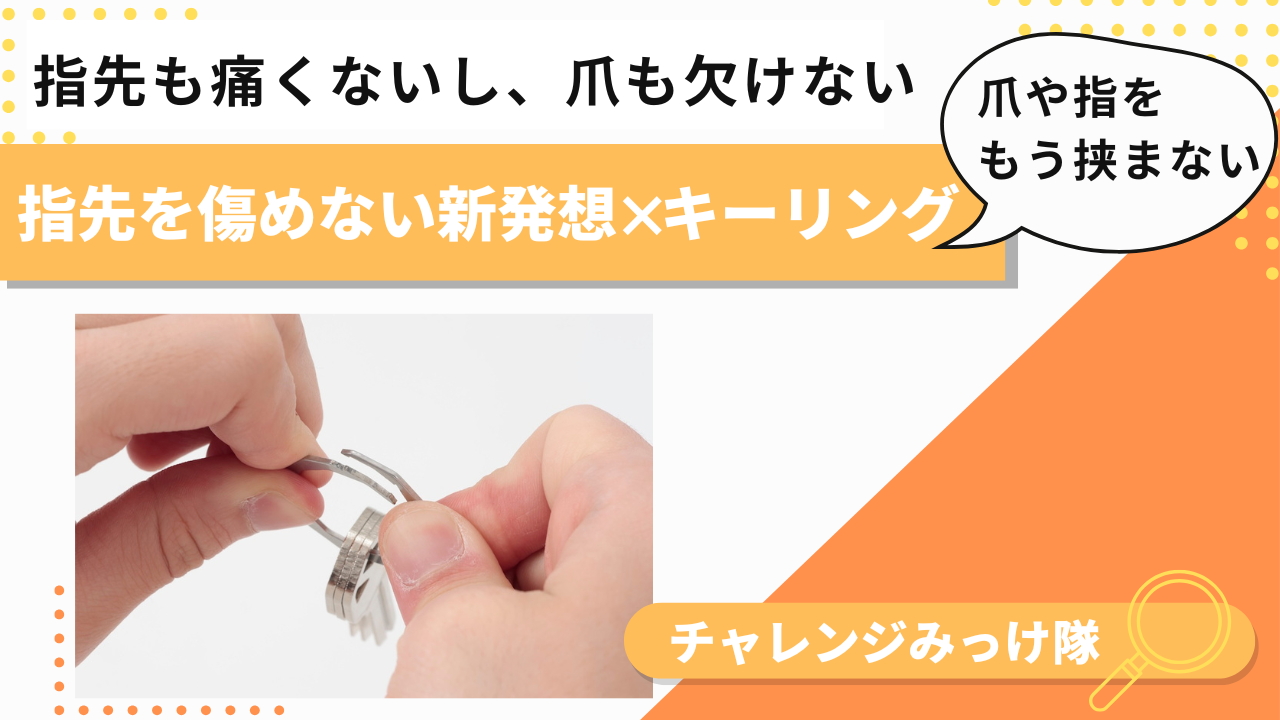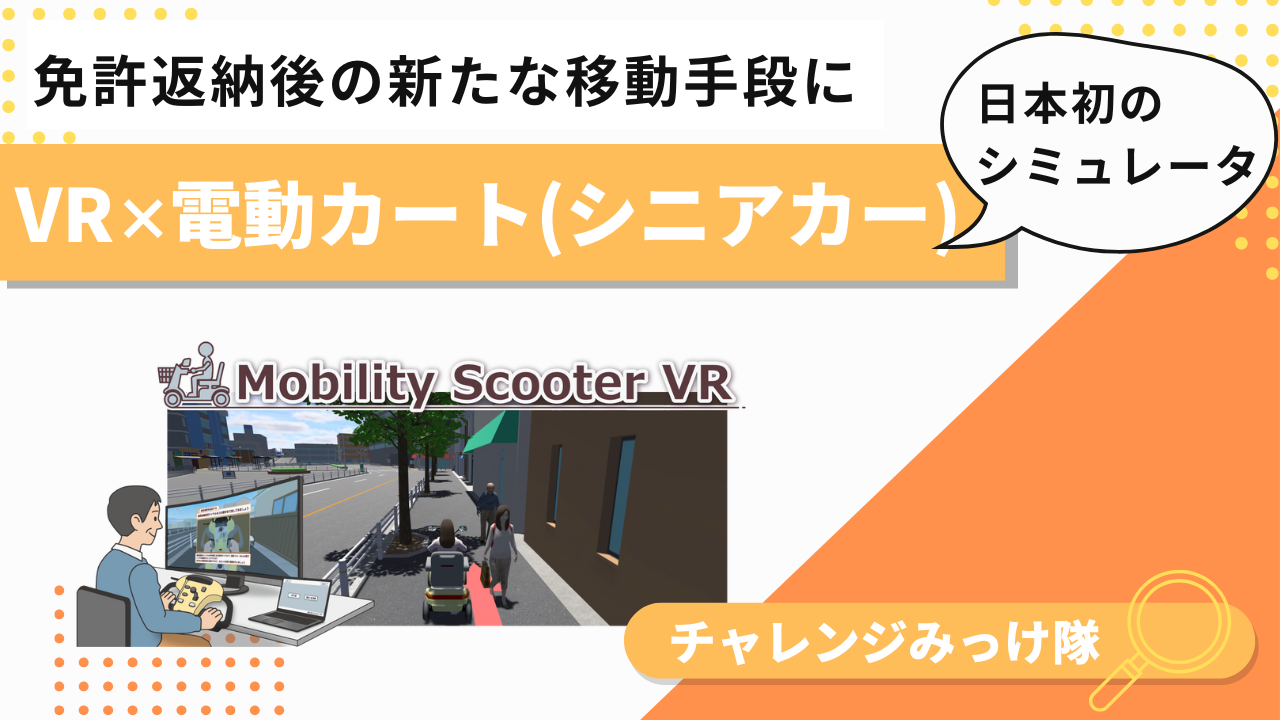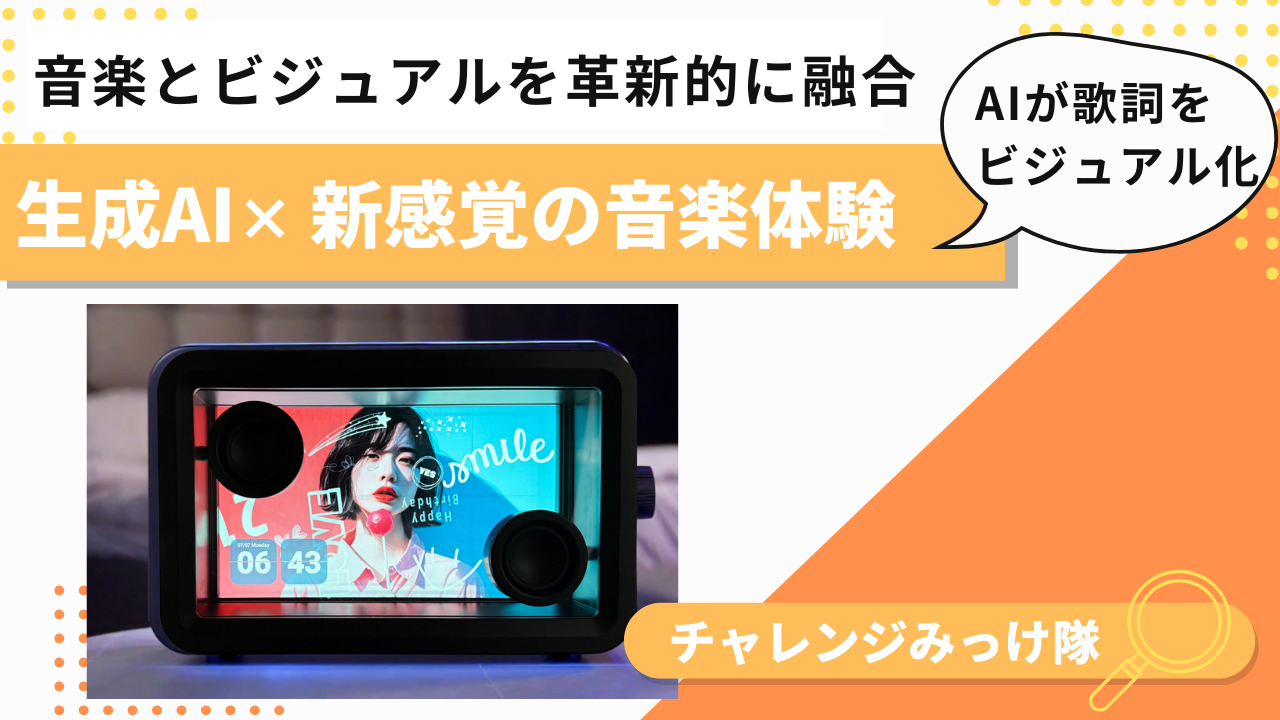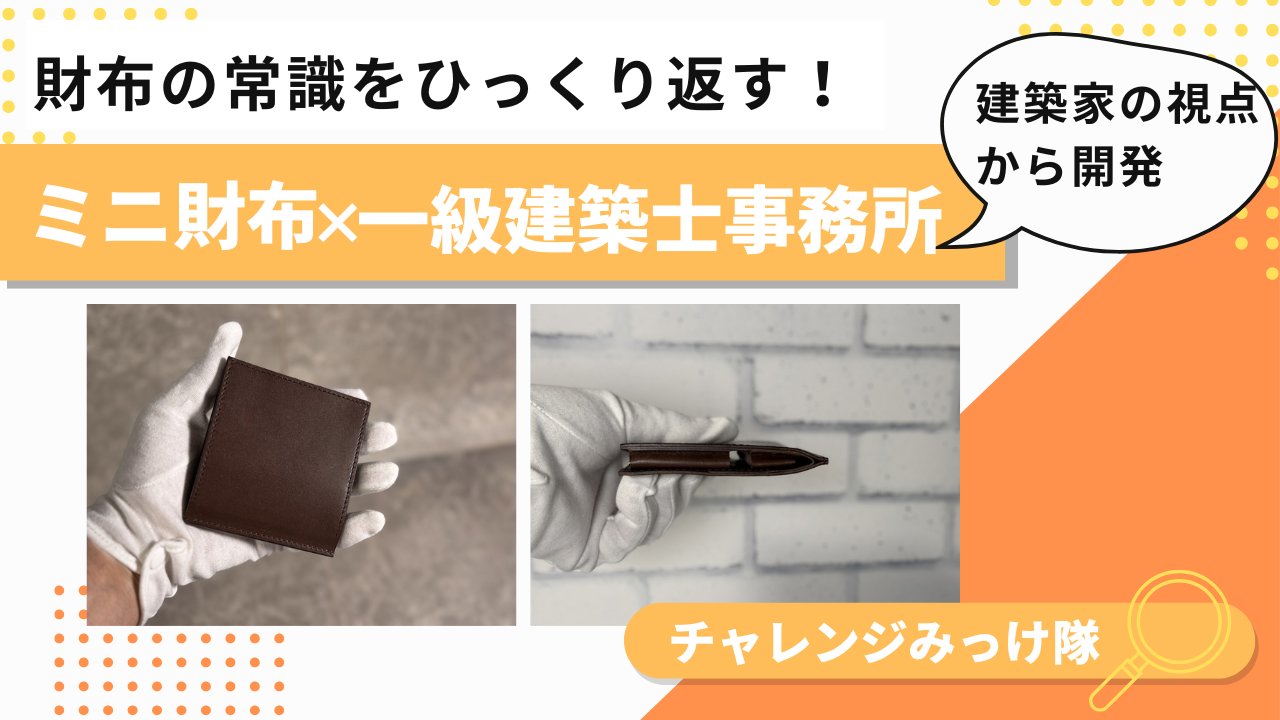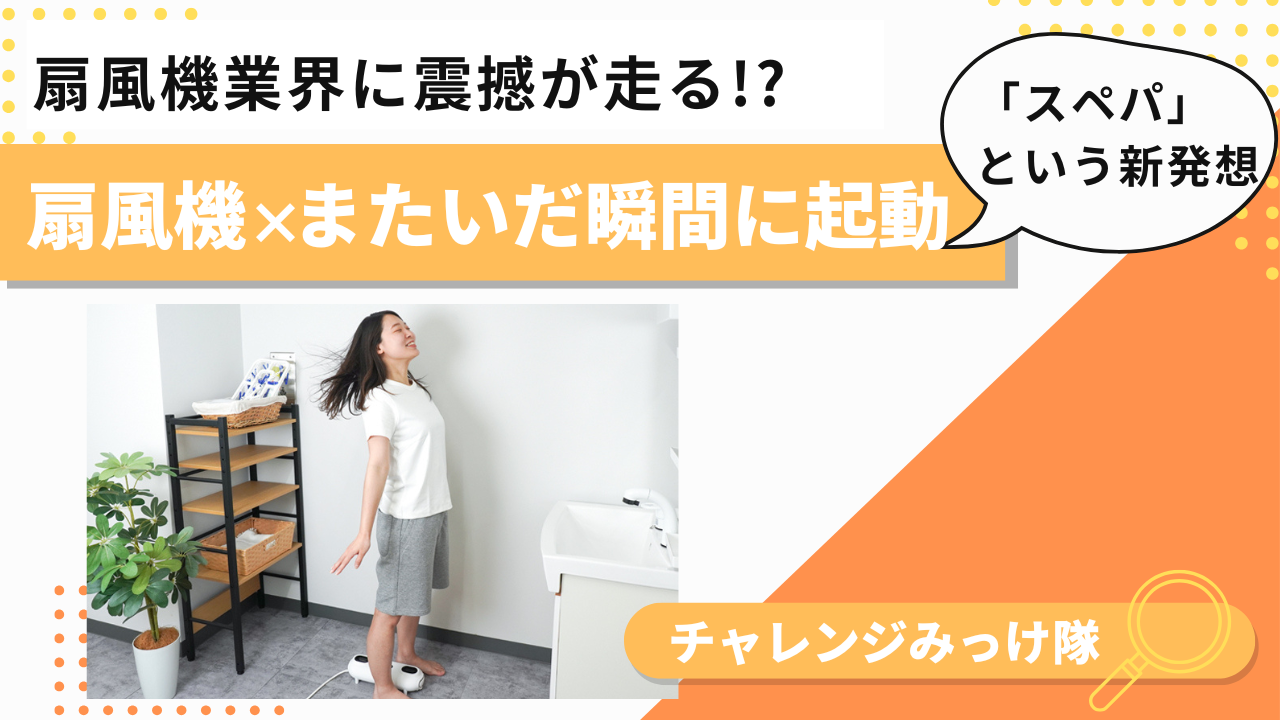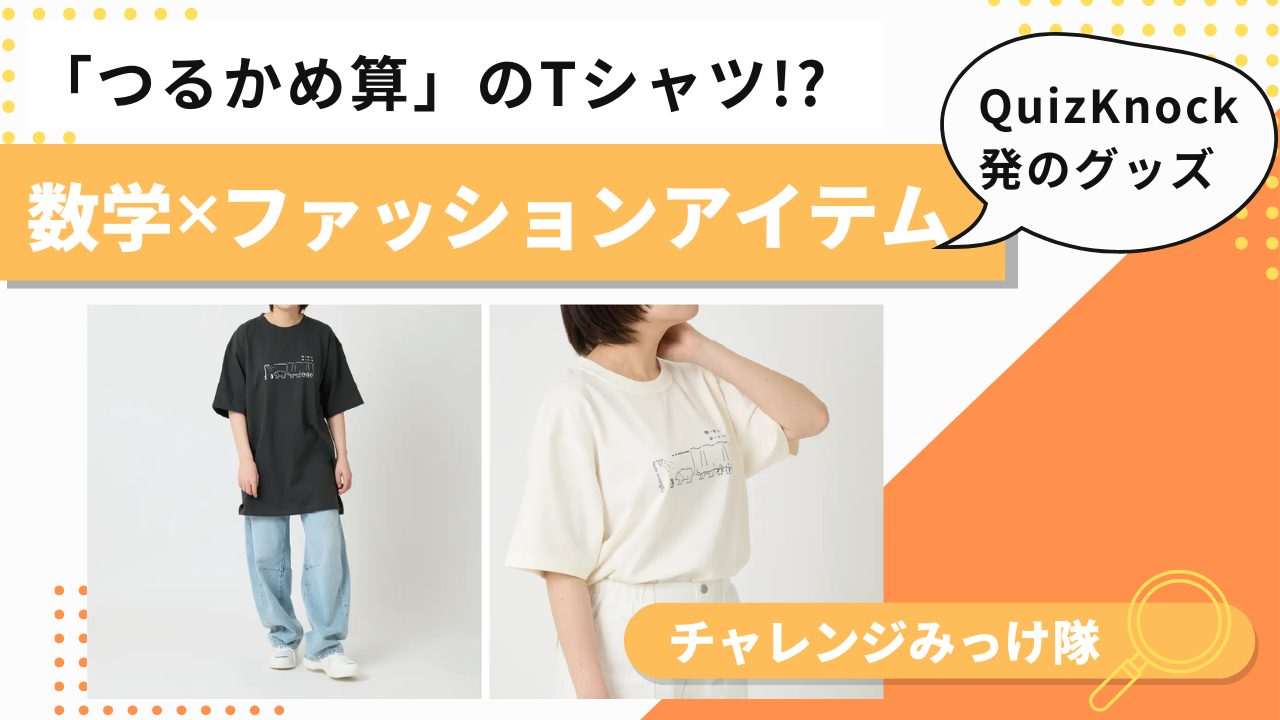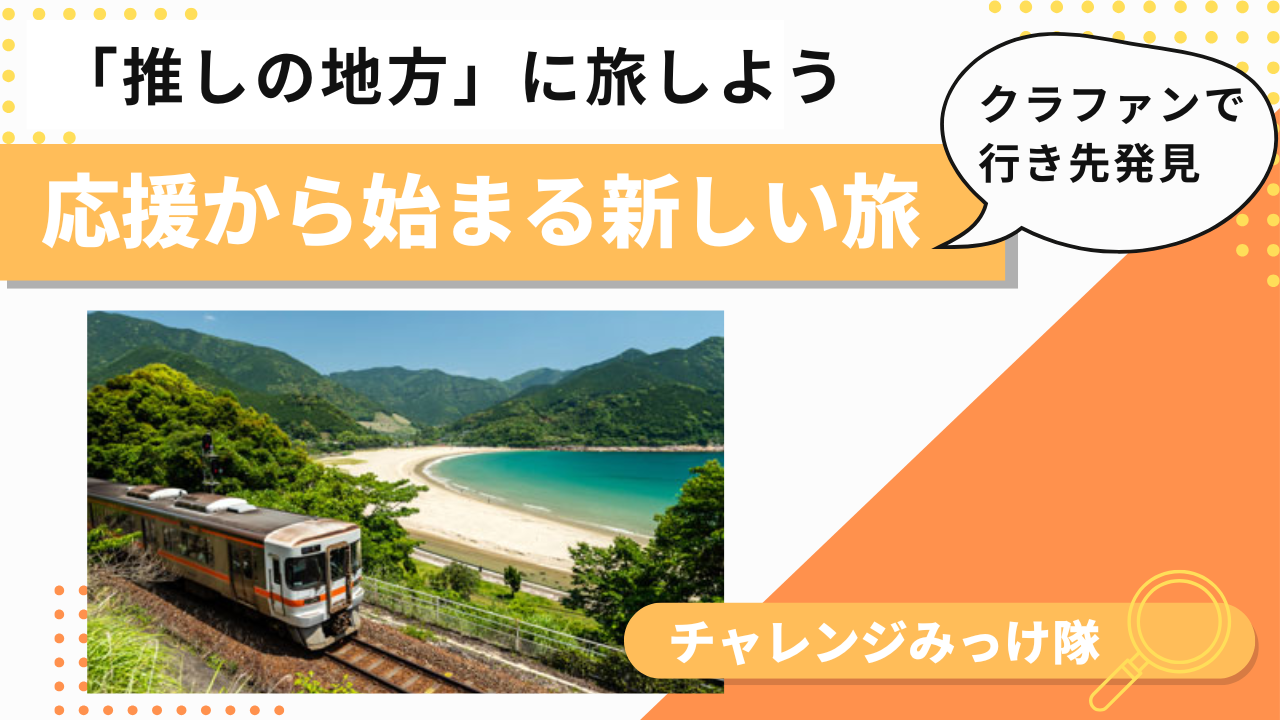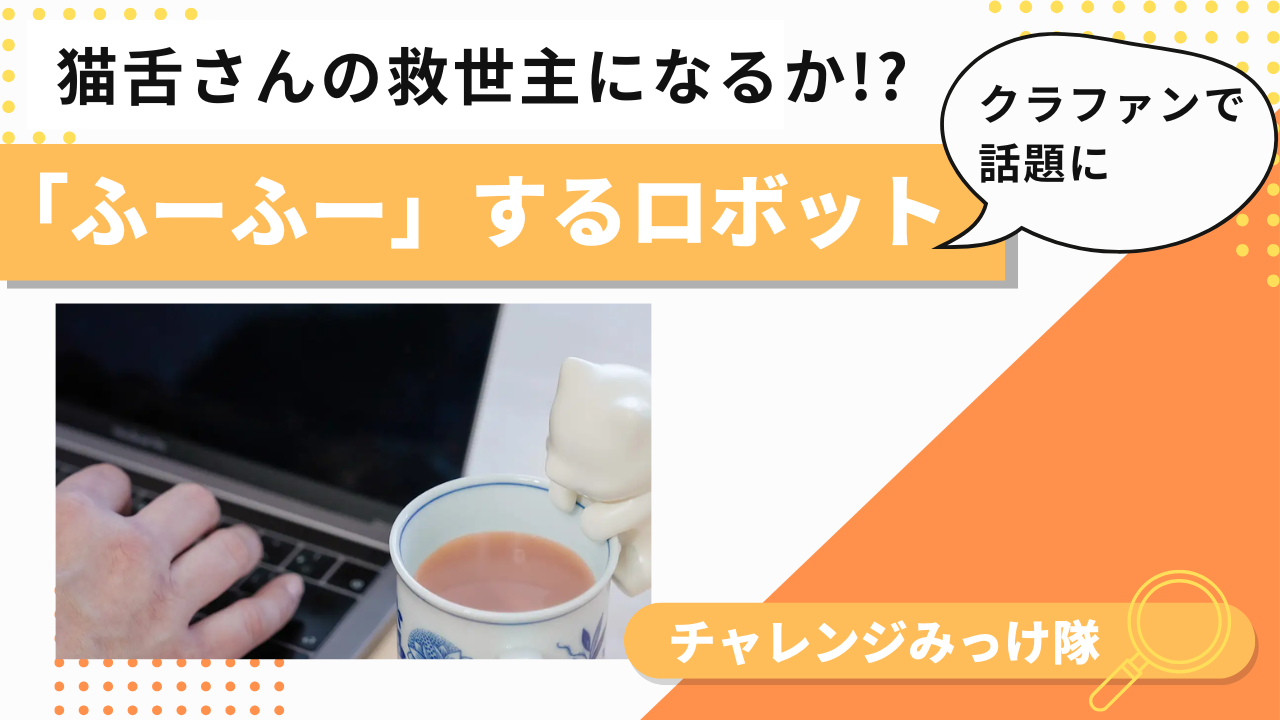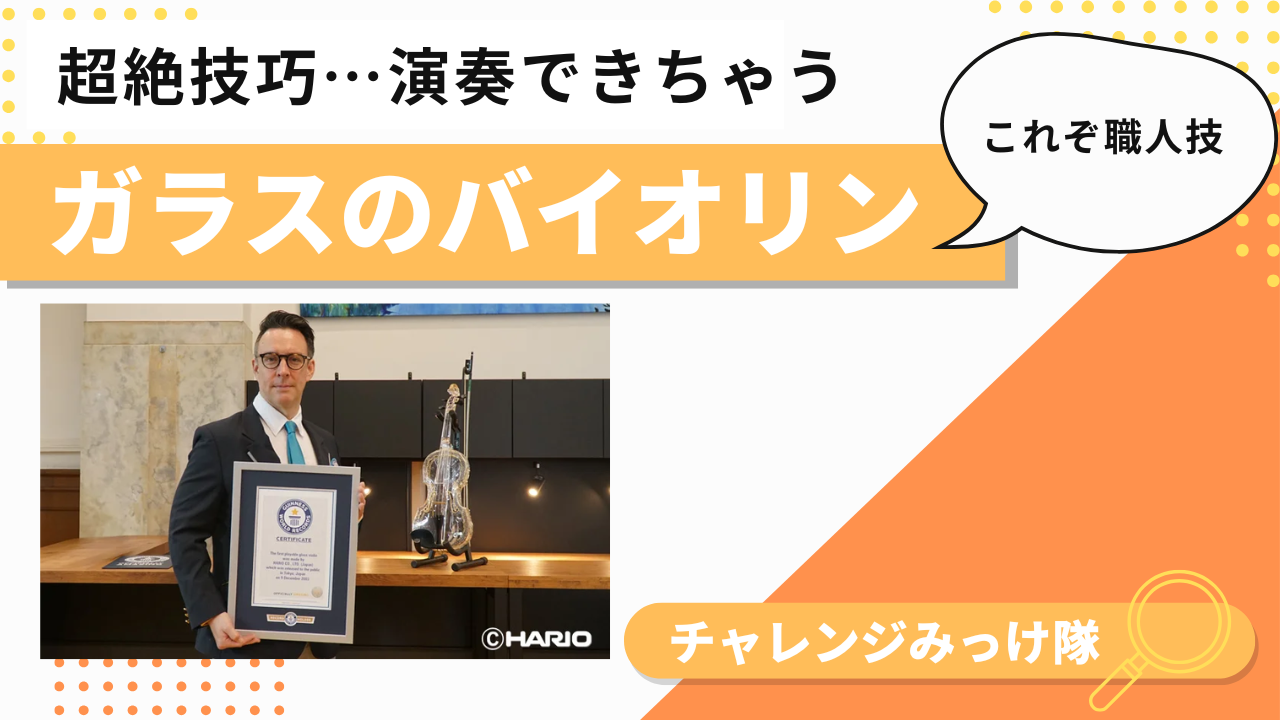新商品の中から、特にチャレンジを感じるアイテムを紹介する『チャレンジみっけ隊』。
今回見つけたのは、なんと価格が10万円もする「体験型ミニトマト」です!

「トマトに10万円!?」
正直、誰でもそう思いますよね。スーパーで買うミニトマトの価格を考えると、もはや現実感がありません。
でも、この価格にはちゃんと理由がありました。この商品は、単なる高級食材ではなく、「生産者自身の時間と物語」を売るという、規格外のコンセプトを打ち出しているんです。この常識破りの価格設定と体験設計に、日本の農業の未来を切り拓くヒントが隠されている予感がしませんか?
ミニトマトの裏側を覗く120分! 生産者の哲学を直接届ける挑戦
この驚きの「体験型ミニトマト」を販売するのは、農業日本一の町・愛知県田原市で農業を営む渥美半島とまとランドです。
同園は、2025年10月10日(トマトの日)より、ミニトマト1.5kgと生産者本人が120分対話する権利をセットにした商品を、価格10万円で販売開始します。
これは単に商品を宅配するのとは違い、生産者自らがミニトマトを直接消費者に届け、農業の価値を生産者の言葉で伝えることを目的とした、これまでにないサービスだといいます。

なぜ、ミニトマトの対価として、常識を超えた「体験」を売るのでしょうか。その背景について同園は、消費者と生産者の間に存在する大きな距離を長年の課題と感じてきたことを挙げています。スーパーに並ぶ野菜の味や価格の裏にある、作り手の想いや哲学、産地のリアルな現状。
この「見えない価値」を可視化するために、商品だけでなく生産者自身の「時間」と「物語」を届けることが不可欠だと考え、今回の企画に踏み切ったのだそう。10万円という価格は、単なるミニトマトの代金ではなく、「生産者と消費者が深く繋がり、日本の農業が抱える現実や未来について語り合う、唯一無二の体験への投資」である、としています。
なお、販売個数は3個限定。
旨みにこだわり、出汁と温泉を与えて育てているオリジナルブランドのミニトマト「出汁推し実(だしおしみ)」を食べながら、開発の背景や農業の未来について語り合えるまたとない機会です。
出典:アットプレス
「コモディティ化」に風穴を開ける! 農業界の価値創造戦略
なぜ『チャレンジみっけ隊』は、この10万円のミニトマトを取り上げたのか。それは、この商品が「農業のコモディティ化(一般化・低価格競争)」という現代的な課題に対して、極めて挑戦的な回答を提示しているからです。

農産物は、多くの場合、価格と品質だけで比較されがちです。しかし、渥美半島とまとランドは、ミニトマトを「食べ物」から「生産者との対話体験」へと価値を転換させました。これは、農家自身による魅力ある商品開発、マーケティング、流通のチャレンジの最先端をいく事例と言えます。
また、価格設定自体が、注目を集める仕掛けになっているのも見逃せません。10万円という圧倒的な数字がメディアやSNSで話題を呼び、結果的に「なぜ10万円なのか」という問いが、プレスリリースの背景にある「生産者の想い」や「農業の課題」にまで光を当てる構造になっているんです。

農家が自身の「時間」を切り売りするのではなく、「価値ある物語」を共有する機会として、価格に生産者の労働価値だけでなく、知恵や哲学の価値を上乗せしている点が、非常にユニークです。これからの時代、消費者は「モノ」だけでなく、「生産の背景」や「物語」にお金を払うという新しい消費の価値観を突きつけられた気がします。
みなさんがお住まいの県、地域では、どのような農家のチャレンジがあるでしょうか?
見かけたら興味を持ってみると面白い発見があるかも知れません。
チャレンジみっけ!
今回見つけたチャレンジは…
- 「モノ」の対価ではなく「生産者の時間と物語」に値付けをした点(価値創造戦略)
- 農産物の流通に「生産者による直接対話とデリバリー」という体験設計を組み込んだ独自性(経験価値創造)
- 常識破りの価格設定で、農業が抱える課題そのものへの関心を喚起するマーケティング手法(ゲリラ・マーケティング)
生産者の「時間」を売るという発想は、農業の単価を引き上げ、後継者不足や労働環境の改善といった課題解決に繋がる、新しい可能性を秘めているかもしれませんね!