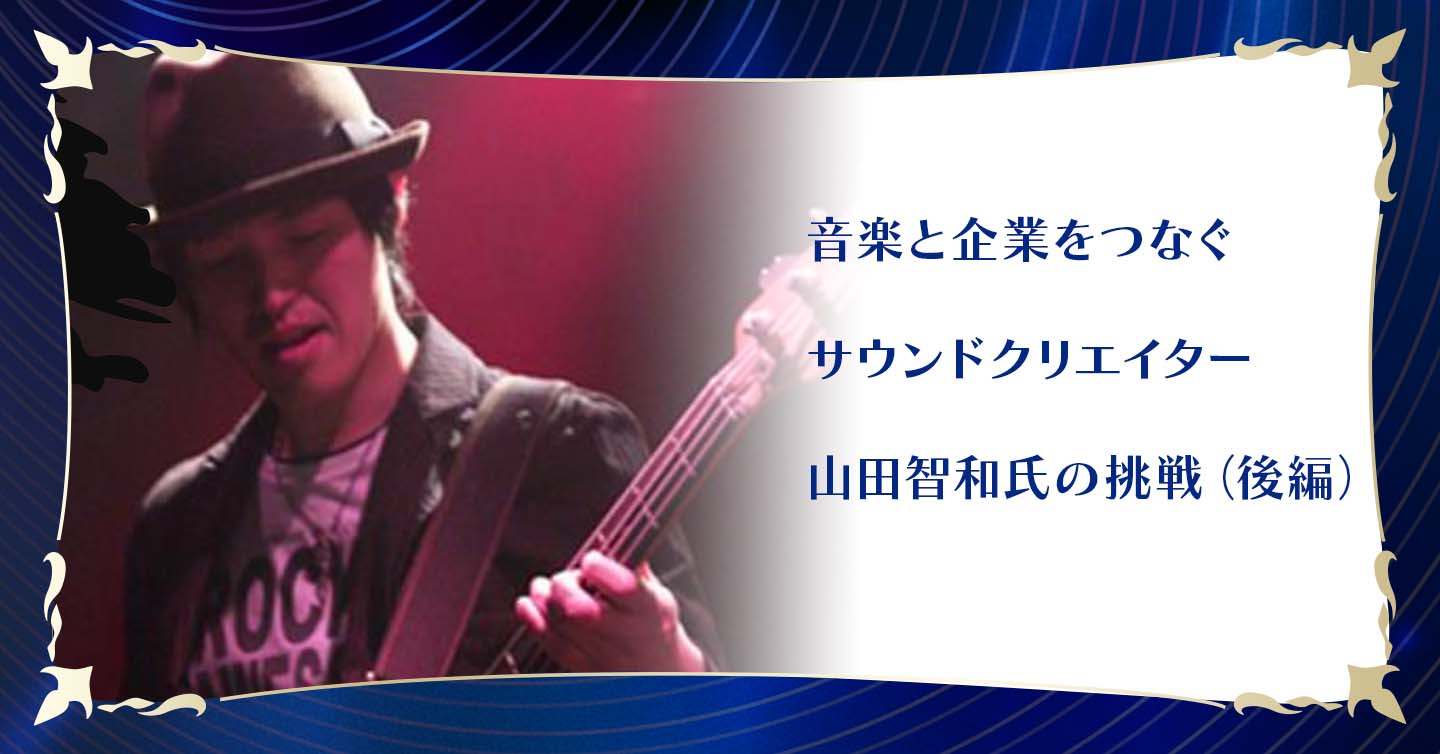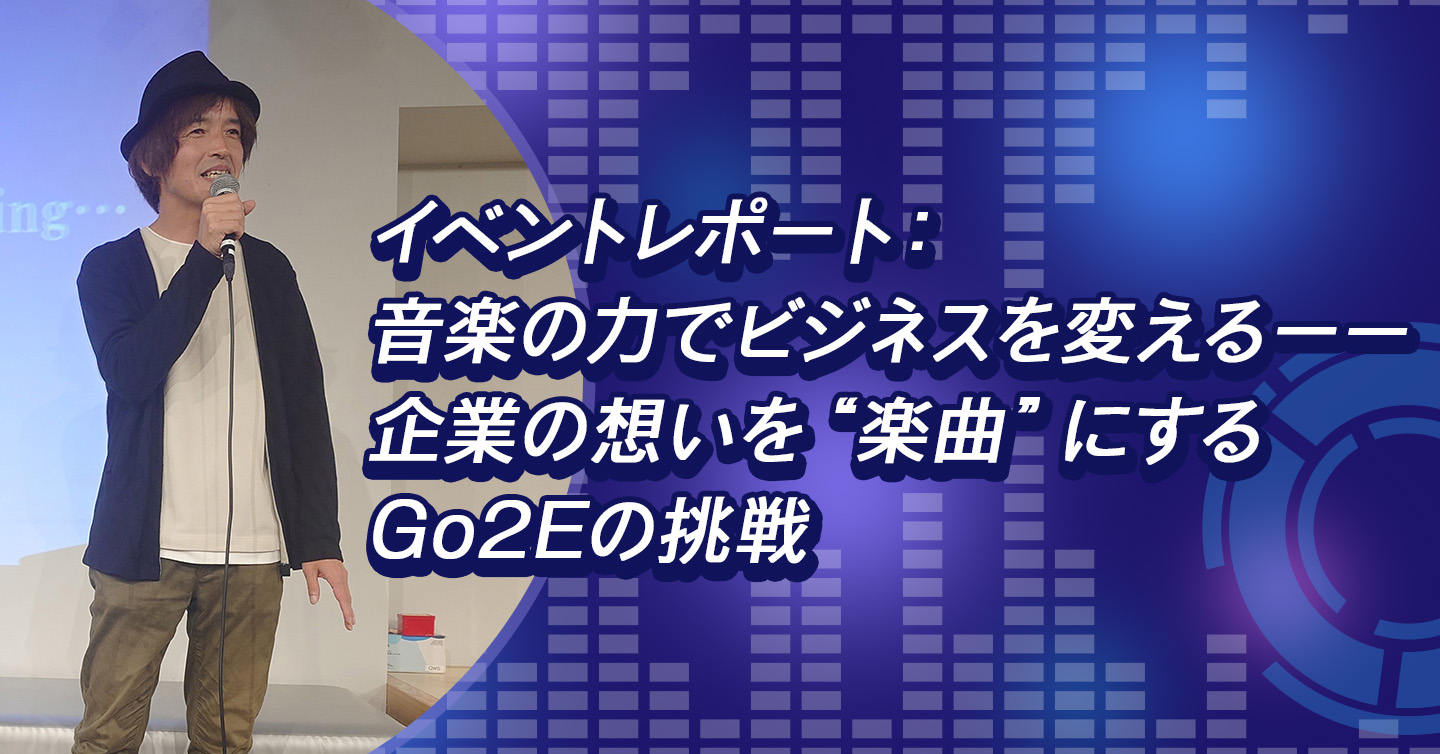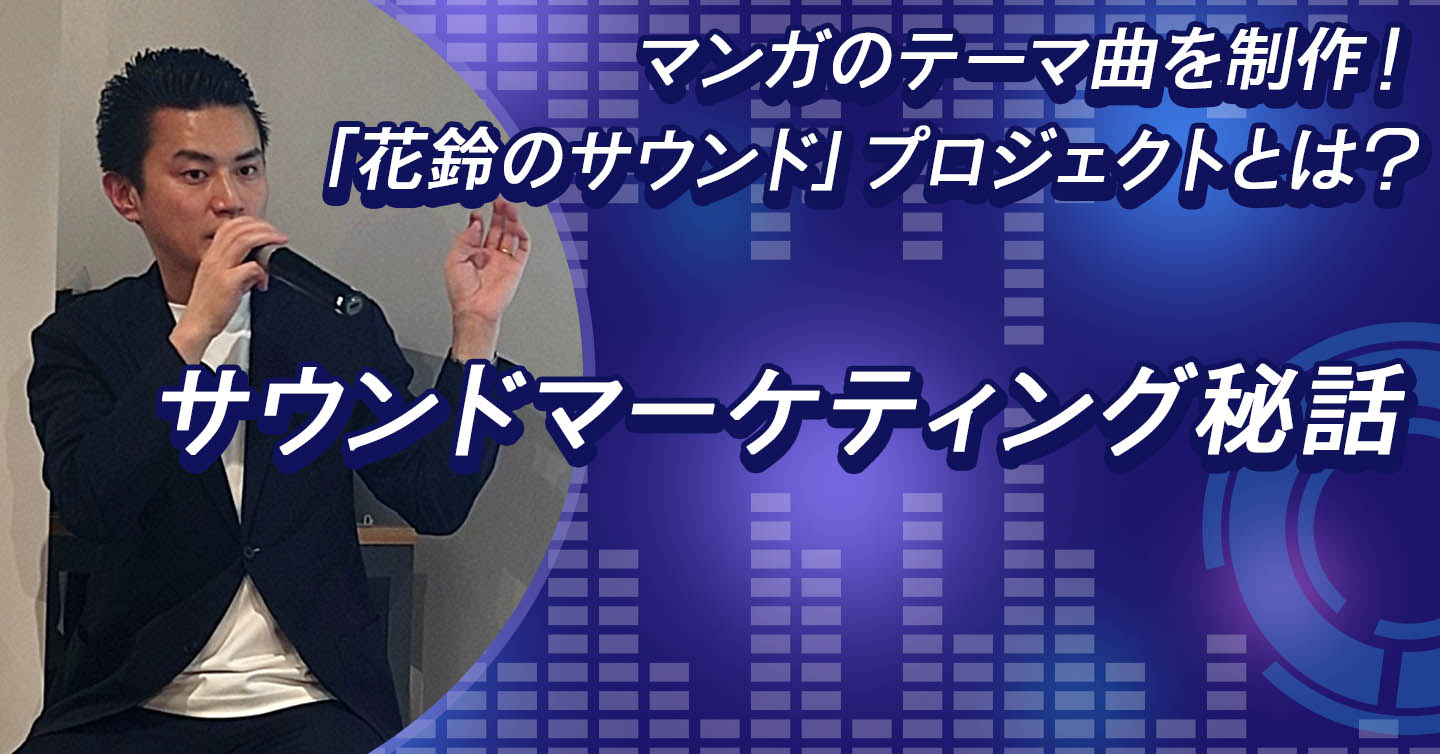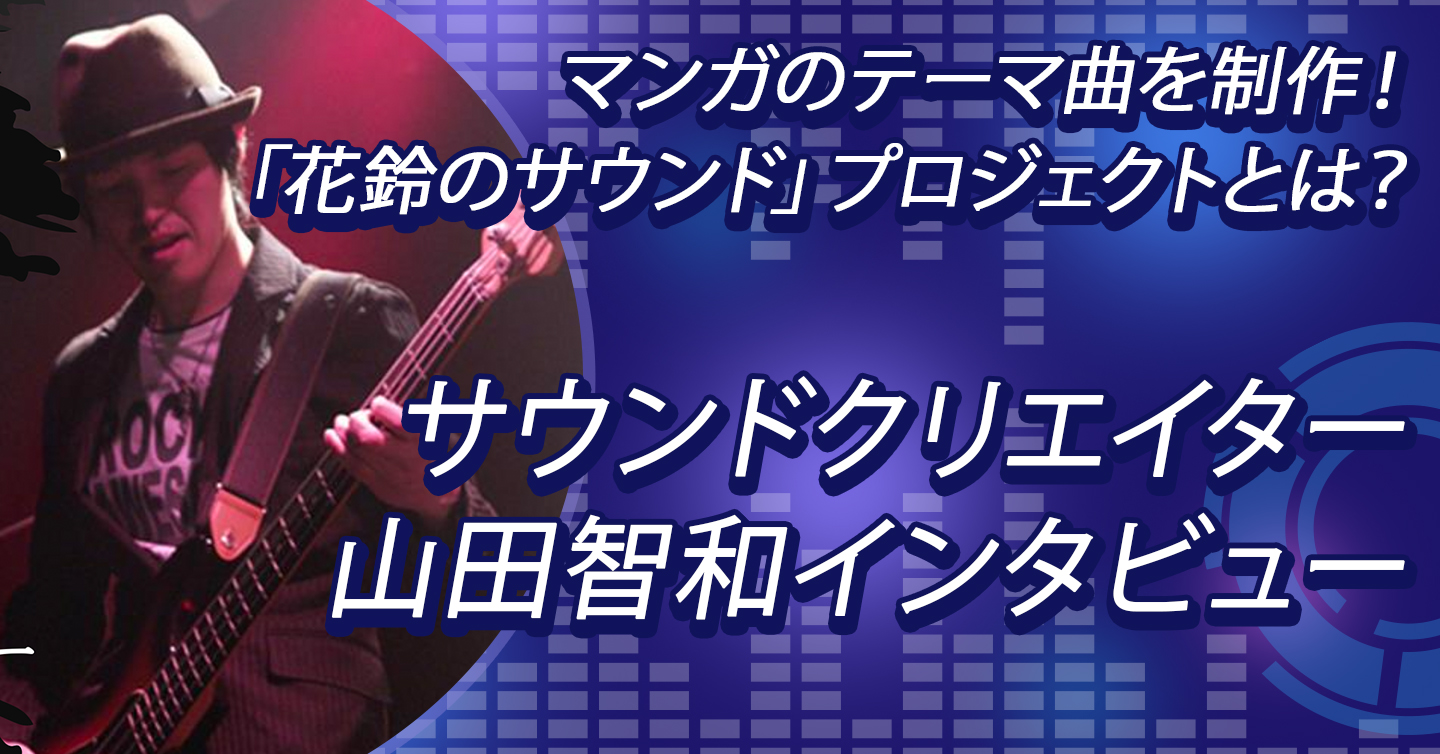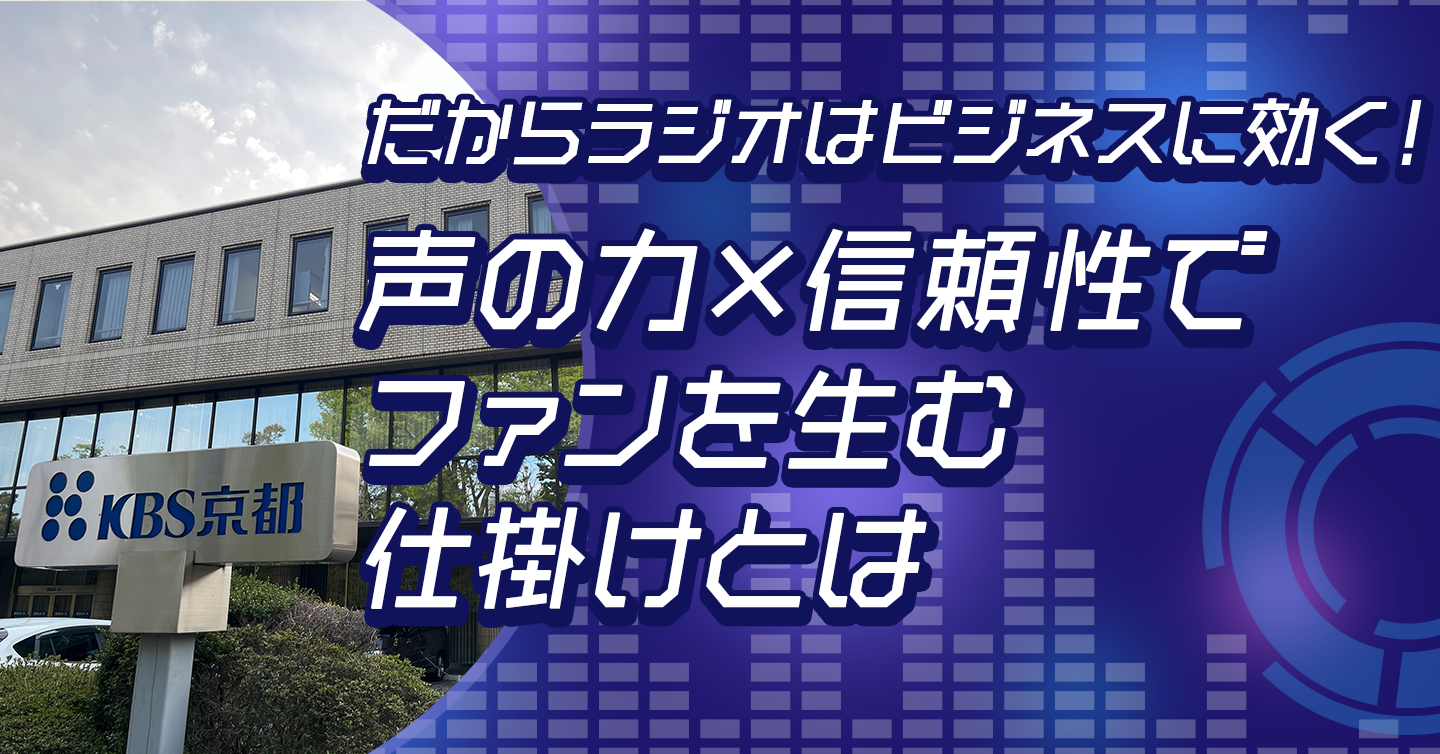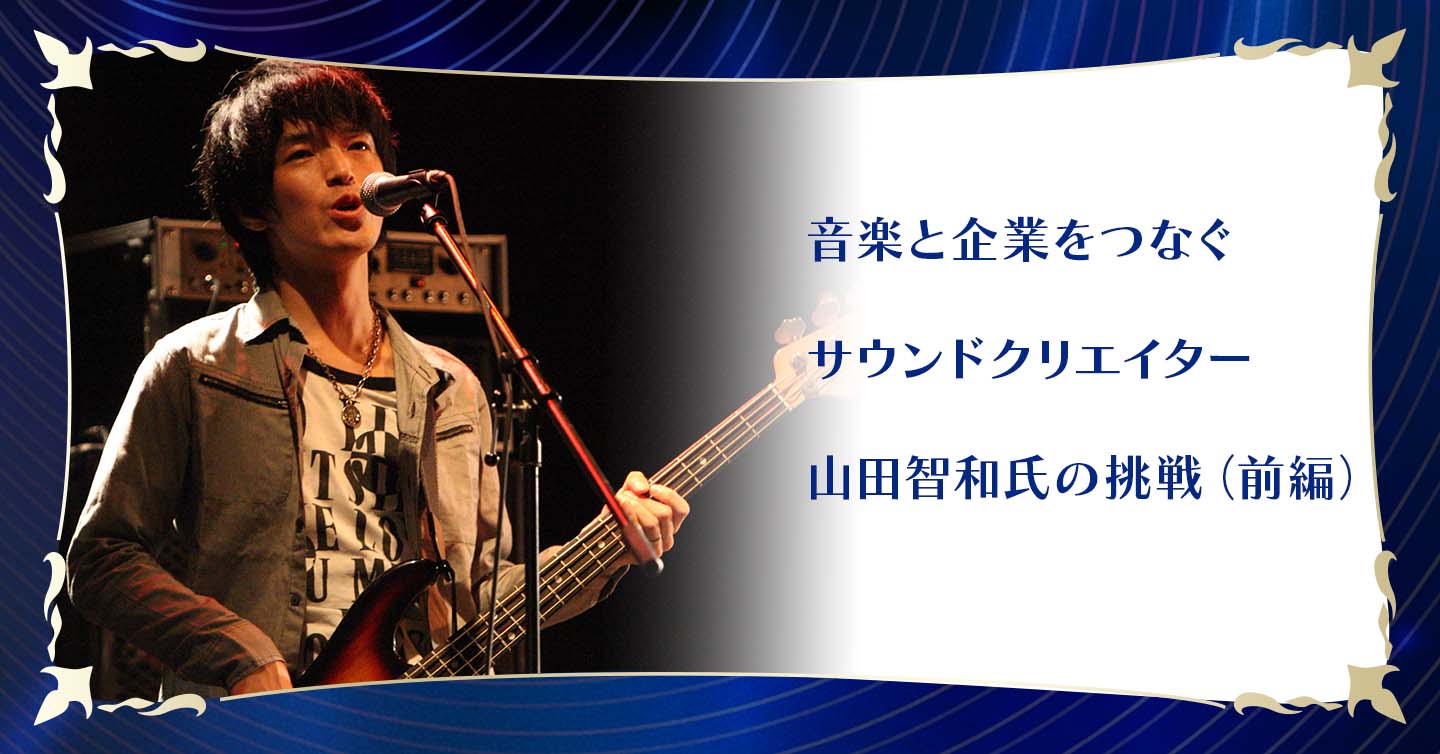前編では、Go2E代表の山田智和氏の音楽との出会い、作曲家としての苦闘の日々、そして「花鈴のサウンド」プロジェクトとの出会いまでを紹介しました。後編では、音楽とビジネスの関わりについて、さらに詳しくお話を伺っていきます。
プロフィール
山田 智和(作曲家・株式会社Go2E代表取締役)
香川県出身、法政大学文学部英文学科卒業。中学2年生の時に、教師と音楽家の夢を抱く。大学卒業後、英語科教員免許を取得し大手学習塾3社の塾講師や、私立高校の非常勤講師、家庭教師で高校・大学受験指導を行いながら音楽家になるべくバンド活動を続け、2008年、トップ声優である小野大輔の1stシングル「雨音」で作曲家デビュー。
以降、AKB48、乃木坂46、SKE48、NMB48、ラストアイドルなどのアイドルグループをはじめ、鈴木雅之、白石麻衣、春奈るな、井口裕香、飯塚雅弓、戸松遥、悠木碧などのアーティスト、アイドルマスター、ラブライブなどの有名アニメへの楽曲提供を行う。2024年10月、株式会社Go2Eの代表取締役に就任。エンターテイメント業界への楽曲提供のほか、企業や自治体への「音」、「音楽」、「映像」を用いた社員教育やプロモーションの支援も行う。
「花鈴のサウンド」プロジェクトの展開

作曲家として18年のキャリアがあり、音楽制作事務所の社長にもなられ、病気がきっかけで考え方が180度変わって、色々な「ビジネスの世界」に飛び込み始めたということですが、そこで出会ったのが、株式会社わかさ生活の社長が取り組んでいる「野球が好き“高校球女”を応援する取り組みである「花鈴のマウンド」というマンガ作品だったんですね。
そうです。
「えっ!? こんなことをしている会社があるんだ」と驚き、色々なことを支援している姿勢を見て
「この社長のような経営者になりたい」という思いが芽生え、わたしができる「音楽」でサポートをさせていただくことになりました。
テーマソング制作について、具体的にはどのような取り組みをされているのでしょうか?
現在もう、曲は完成しています。
プロモーション用の動画も複数制作中です。
楽しみにしていてください!(笑)
楽曲制作でこだわったポイントはありますか?
今の若い人向けの楽曲は難しいものが多いんですよ。
私が青春時代に聞いていたものとは全然違います。
そこであえて逆の方向に行って「とにかく分かりやすいもの」を目指しました。
ストレートに「誰かを応援したい」という気持ちが伝わるようなものにしたかったんです。
この音楽を通して、どのようなことが起こると嬉しいですか?
最近、いろいろな分野の方とお話する機会が増えているのですが、先日、女性の神主さんと知り合う機会がありました。
その人は、偶然にも「うちの娘が野球をやっているんです」という方で。
いま中学3年生で次は高校生になるけれど、東京で女子野球部がある学校がほとんど無くて、続けたくても続けさせてあげられないと。
その方に、今回作った曲と動画を見せたら、泣きそうなくらい感動してくれたんです。
好きなことを続けさせてあげられない親御さんの気持ちに響いたんだと思います。
このプロジェクトを通して、私たちが作ったテーマソングや動画が広まることで、女子野球という競技自体のイメージも広がると思うんです。
多くの人に耳にしてもらい、目にしてもらうことで「女子野球の世界」の印象が浸透していく。
そうすれば、女子野球をやっている人、その家族、関係者の人たちも、もっと嬉しく、誇らしく夢を追いかけたり、楽しんだりしてくれるようになるかもしれない。
「音楽の力」で、間接的にそういう変化を後押しできればいいなと考えています。
音楽を企業活動に活かす新たな試み
作曲を手掛けた「ラブライブ! スーパースター!!」ED主題歌・Liella!「未来は風のように」
現在、「花鈴のサウンド」プロジェクト以外にも「音楽を企業活動に活かす」取り組みに着手されているとか。
はい。ある自動車メーカーが主催する地域貢献プロジェクトのテーマソング制作に関わっています。
地元の放送局がサポートに入っているのですが、そのテレビ局のプロデューサーさんから「このプロジェクト自体にテーマソングがあった方がいいのでは」とアイデアを頂きまして。企業側もすぐに「それはいいね!」と乗ってくださって、曲を制作することになりました。
こうした「プロジェクト」にテーマソングがあることの意味は、何だと思いますか?
地元放送局がこのプロジェクトを1年間追っていく予定なんですが、そこで毎回テーマソングが流れれば、活動自体に興味がない視聴者でも「あの音楽が流れたら、あの活動のことだ」とすぐ想起できます。
また、長期的な効果として、子どもたちが大きくなって久しぶりにYouTubeなどでその曲を聞いたときに、「あのとき一緒にゴミ拾いをしたな」とか「交通安全ルールを教えてもらったな」という記憶が蘇るんです。
「音楽」は、その時の記憶ととても強く結びつくもので。
子どもの頃に聞いてた童謡とか、保育園の歌とか小学校の校歌、何十年たっても歌えたりしませんか?
で、歌っているとその歌のアニメ映像が思い出されたり、学校の体育館のこと思い出したり、その繋がりで友人の事、卒業式のことを思い出したり。
音楽は「感情と記憶を結び付けて、深く心を動かす」トリガーになるんです。
なので、このプロジェクト自体が終わったとしても、その体験は音楽とともに残り続ける。
それが将来、「自分たちも同じようなことをやってみよう」というきっかけになるかもしれません。
企業と音楽というと、昔は「社歌」が一般的でしたが、今のお話は全く違う形の音楽活用ですね。
そうですね。従来の社歌は内向きなものでしたが、これからは外向きのブランディングとしての社歌、つまり企業が社会にどう貢献していきたいかを表現するような音楽が重要になると感じています。
今はSNSなどで簡単に発信できる時代ですし、プロが関わることでクオリティの高いものができます。
音楽が持つビジネス価値
企業にとって音楽やサウンドはどのような価値があるのでしょうか?
例えばドラッグストアで目薬を選ぶとします。
自分もそうなんですが、細かい成分の違いなんかはよく分かりませんよね。
でも、あるCMソングが「頭の中」で流れてきて、
「やっぱりこのブランドにしよう」と選んでしまうことがある。
製品自体は競合と大差ないことも多いと思うんです。
特に自分があまり関心がない分野のものならなおさら。
そのとき、音楽という全く違う要素を絡めることで、他との差別化が図れるんですね。
音や音楽がなぜそれほど強い影響力を持つのでしょうか?
パソコンの起動音やメールを受信したときの効果音など、例を上げるときりがないですが、海外ではそうしたものはソニックロゴ(音のロゴ)として知られています。企業やサービスのイメージと、強く結びついていますよね。
音は視覚と並んで重要な感覚で「人の記憶に残りやすい」という特徴があります。
脳に直接感情を想起させる力があるんです。
マーケティングの世界でも、スーパーマーケットでどんな音楽を流すかによって、お客さんの滞在時間や購買行動が変わるという研究もあります。
「音の力」、「音楽の力」ってとても強くて、人間の本能を動かすパワーを秘めているんです。
若手クリエイターの育成と音楽業界の未来
作曲を手掛けたSCANDAL「Brand new wave」
Go2Eとして今後取り組みたいことは何ですか?
今後は音楽をビジネスやマーケティングに活用する企業を増やして、音楽業界全体のニーズを高めていきたいと考えています。企業案件を増やすことで、潜在的なニーズを掘り起こすことが重要だと思っています。
企業の中で「音楽は必要不可欠なもの」という認識が広がれば、作曲家やクリエイターの仕事も増えていきます。音楽制作のマーケット自体を大きくすることが、若手クリエイターの活躍の場を広げることにもつながるんです。
私自身、コンペでの苦労を経験してきたからこそ、次の世代のクリエイターが安定して活動できる環境を作りたいという思いがあります。
何より「音」の持つ力を様々な企業や組織に活用してもらうことで、社会全体にとっても大きなプラスになると信じています。企業と音楽をつなぐ架け橋になりたいですね。
音楽業界の若手にとって、現在はどのような課題があるのでしょうか?
音楽業界の構造が大きく変わってきています。
今の若い音楽クリエイターたちは、私がやってきたようなコンペ形式の仕事に魅力を感じない傾向があるんです。
SNSで曲をアップしてバズれば注目される時代ですから、「一生懸命作った曲が採用されなければ収入にならない」というコンペのシステムは、彼らにとって非効率的に映るんでしょうね。
だからこそ、若い人たちに「音楽を作る仕事」に夢を持ち続けてもらうためには、コンペだけに頼らない安定した仕事の場を増やすことが大切なんだと思っているんです。
企業の音楽ニーズを掘り起こし、クリエイターが才能を発揮できる新しい場を作っていきたいですね。
企業と音楽をつなぐことで、クリエイターの活躍の場も広がるわけですね。
そうなんです。企業の中で「音楽はマストで必要だ」という認識が広がれば、コンペで戦うだけでなく、企業案件を安定的に受けられる土壌ができます。そうすることで、音楽業界全体が活性化し、若手クリエイターにも夢を持って入ってきてもらえると思うんです。
みんながハッピーでクリエイティブな環境を作りたい。それが私のビジョンです。
音で繋がる、新しい可能性
インタビューを終えて、音楽とビジネスを繋ぐことで生まれる新たな可能性を強く感じました。企業ブランディングに音楽を活用する事例はまだ少ないかもしれませんが、音が持つ力を活かせば、多くの企業や団体にとって大きな武器になるはずです。
今回インタビューの中で山田さんが語った「花鈴のサウンド」プロジェクト。あくまでもそれは、音楽が持つ可能性の一例に過ぎません。企業のブランディングやプロジェクトの認知向上、そして社内外の一体感の醸成など、音楽の活用法は多岐にわたります。そうした音楽の力をビジネスの現場に取り入れていく。そこから新たな価値が生まれていくのではないでしょうか。
音楽制作のニーズを広げ、若手クリエイターの活躍の場を作り、みんながクリエイティブに進める環境づくり——。音の持つ可能性を追求する山田さんの挑戦は、まだ始まったばかりです。