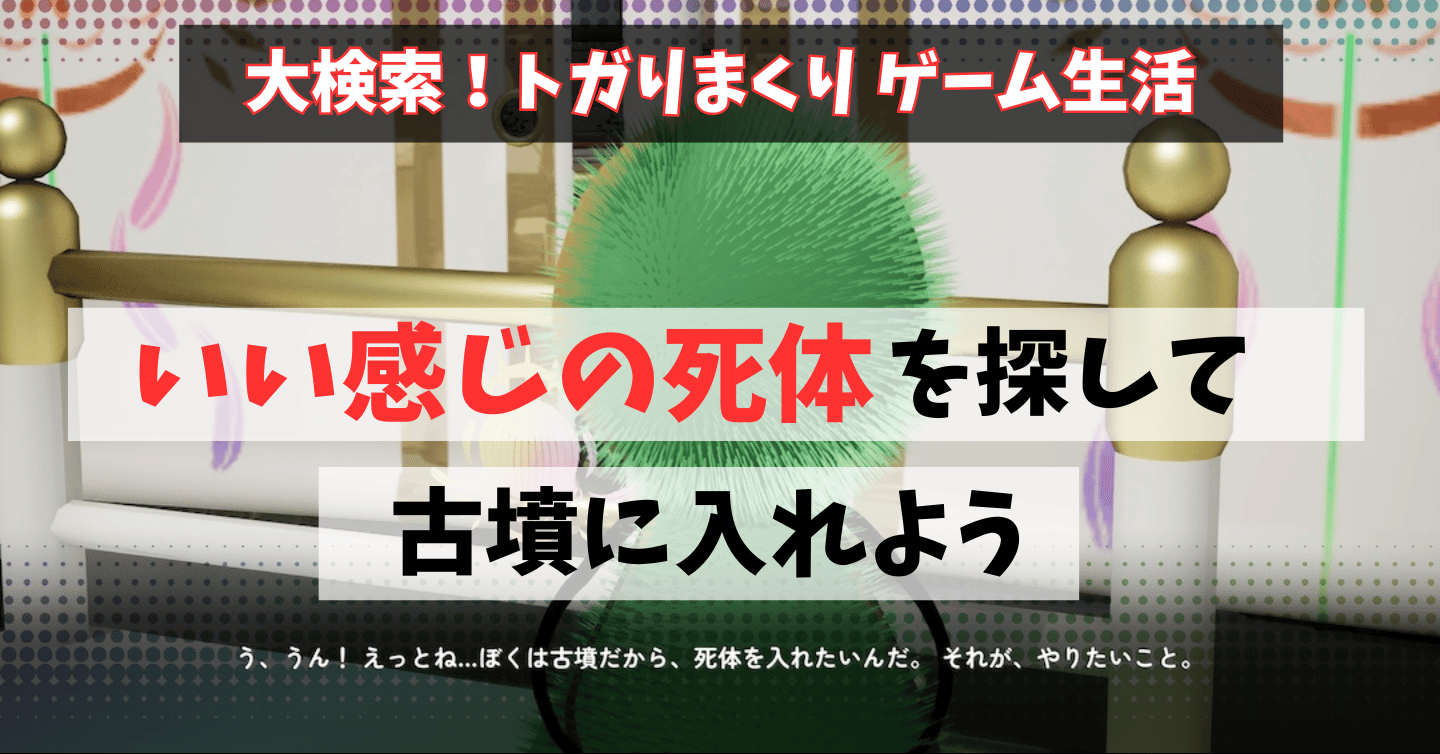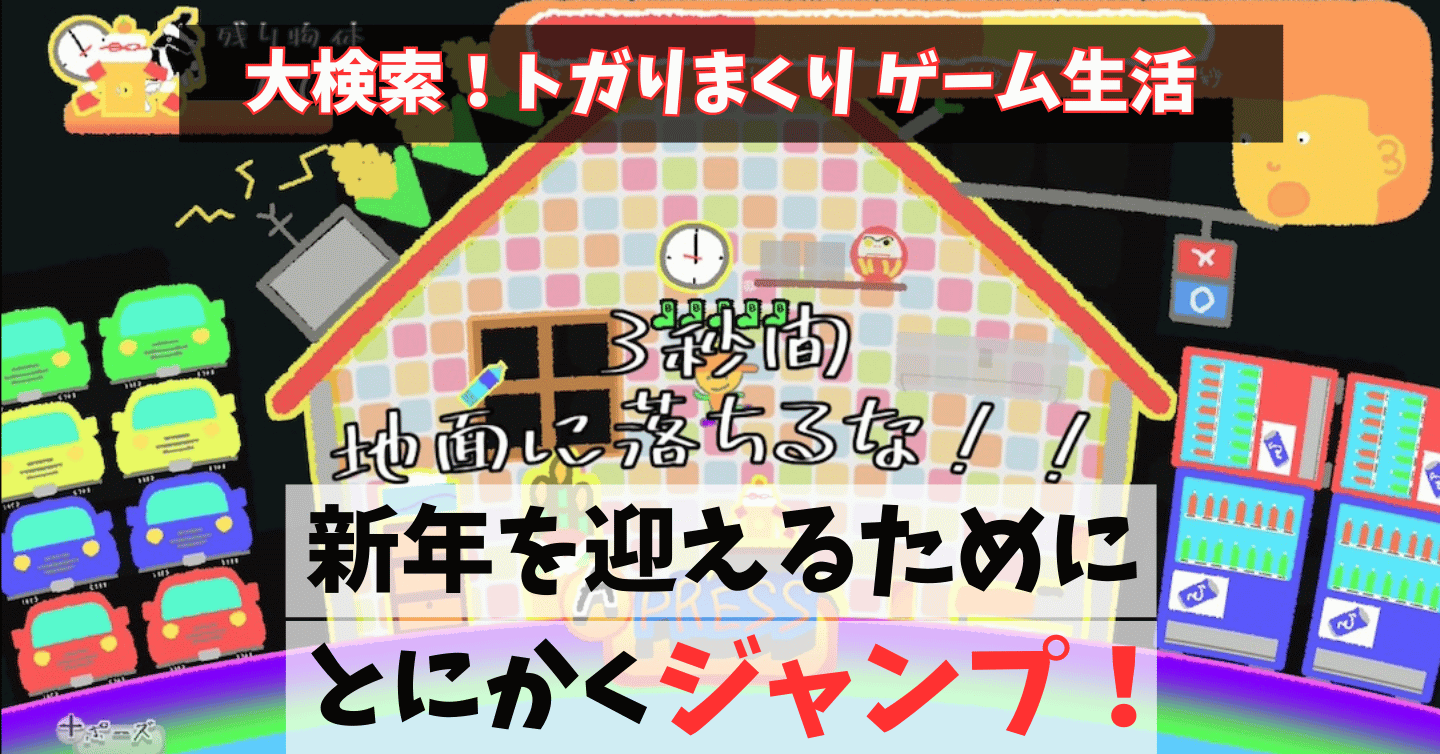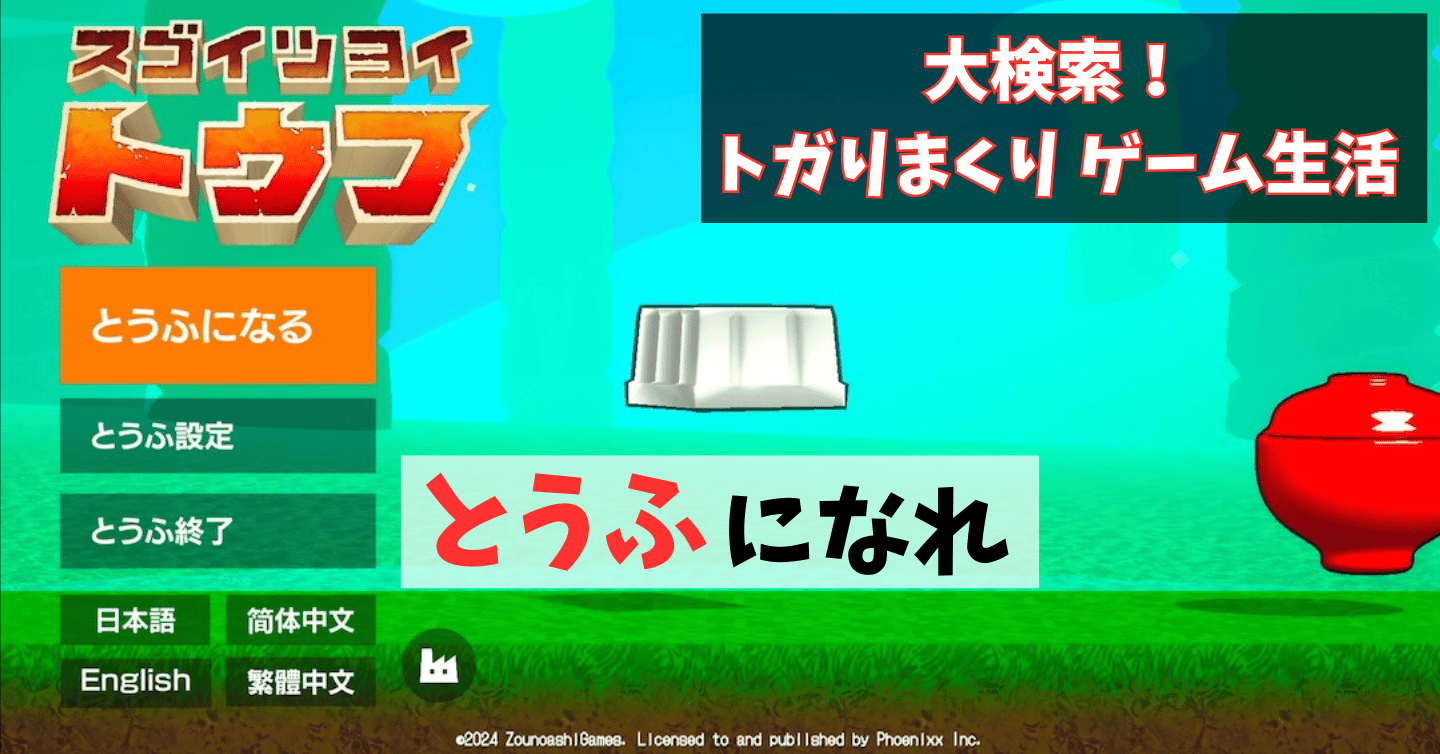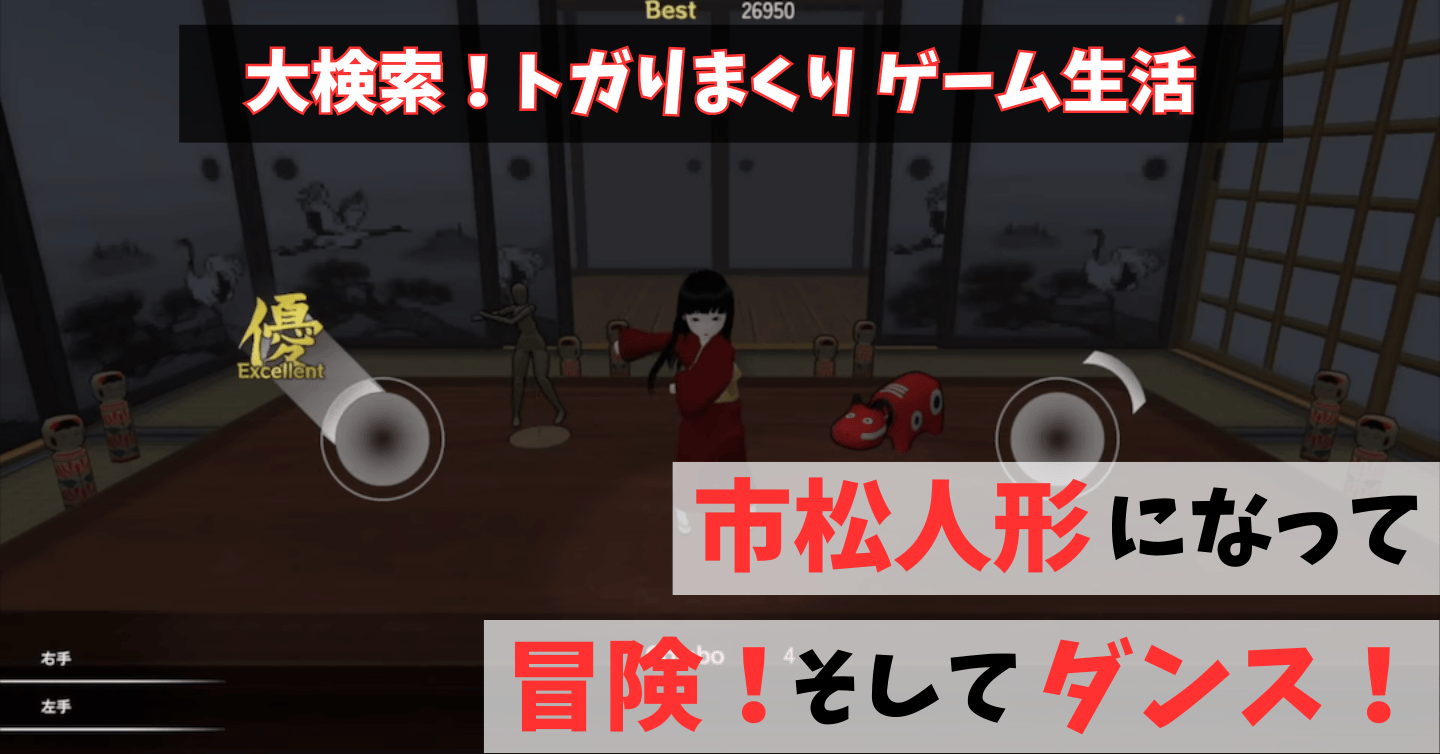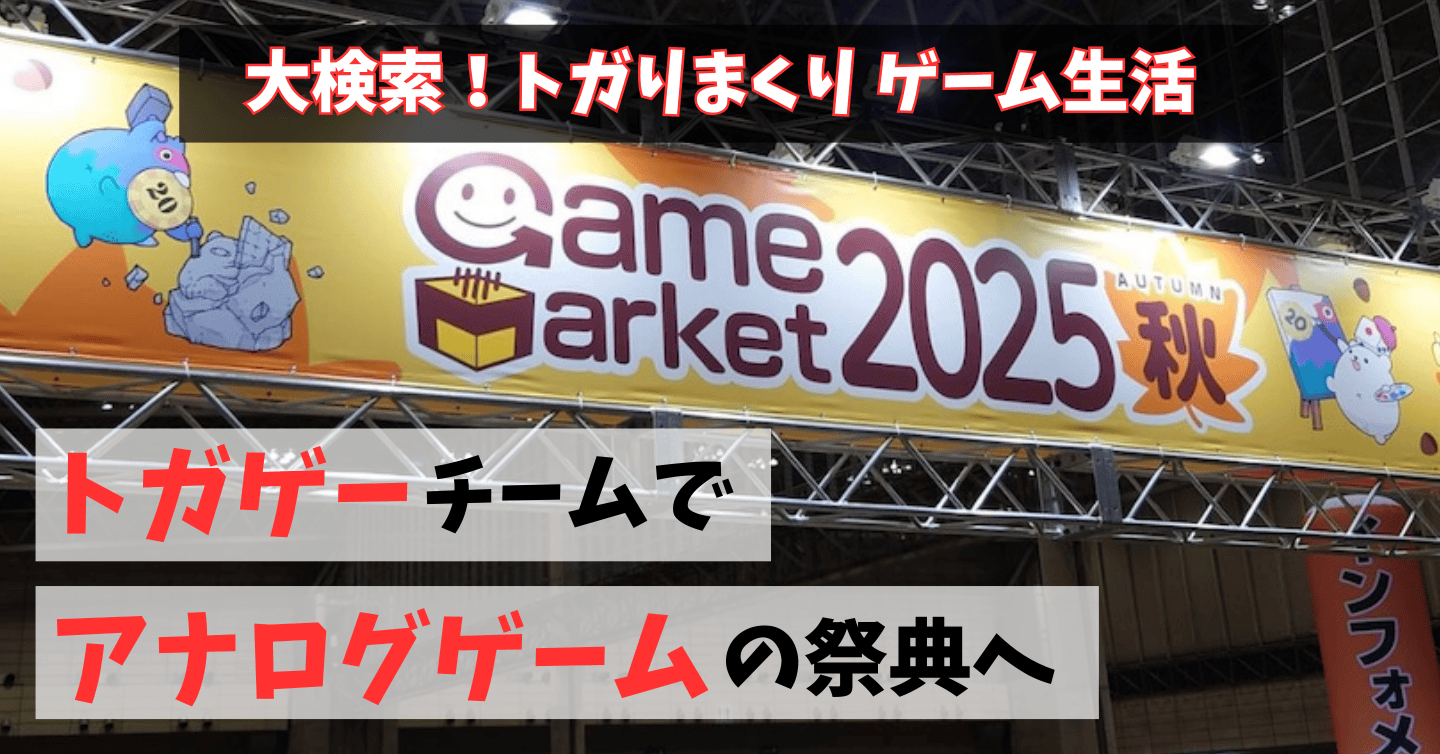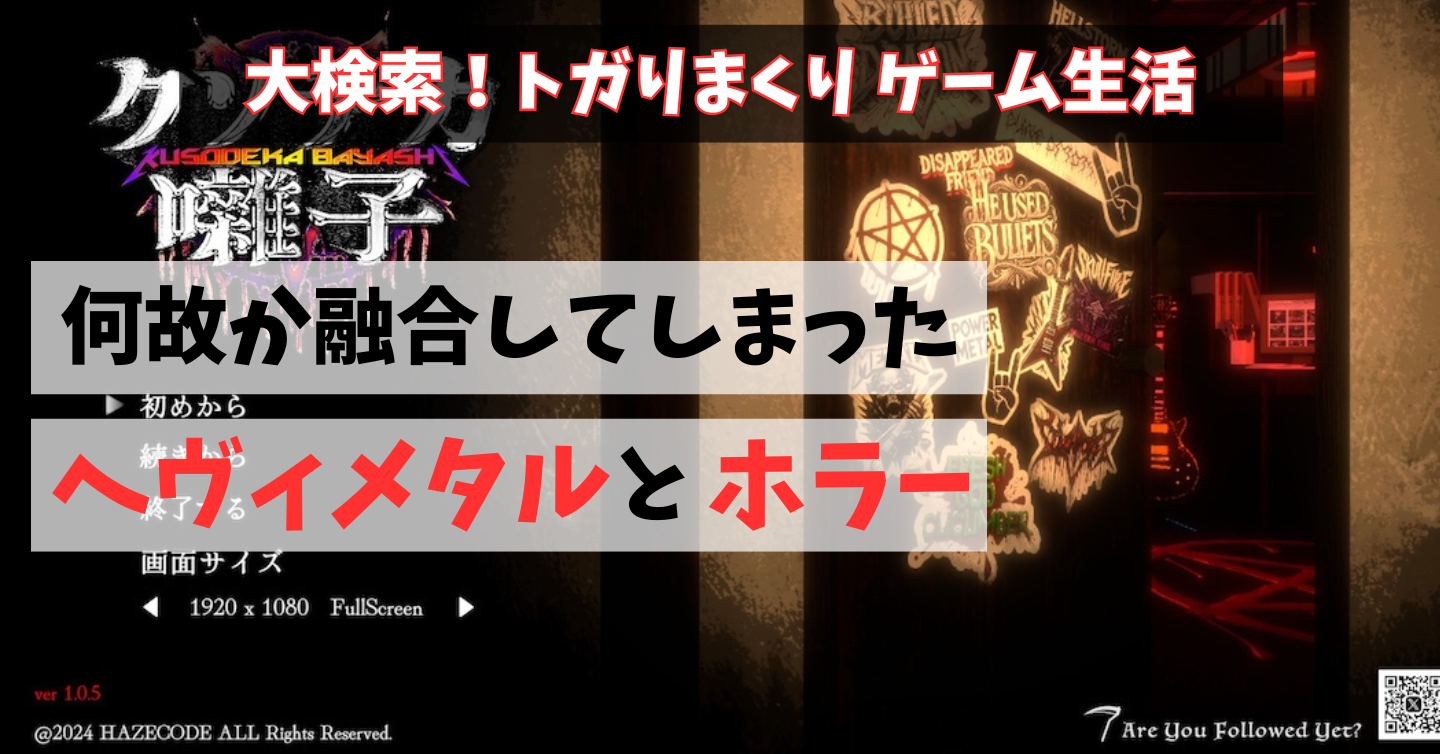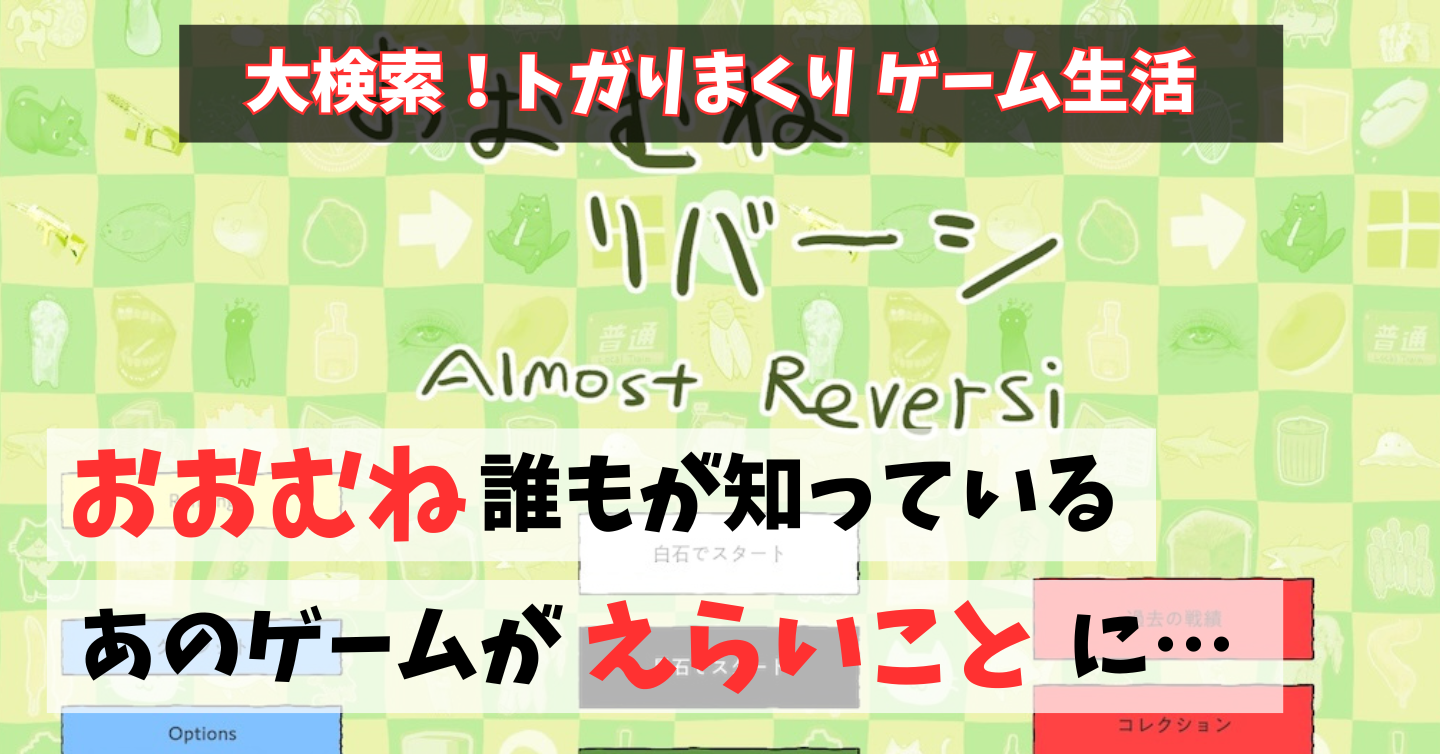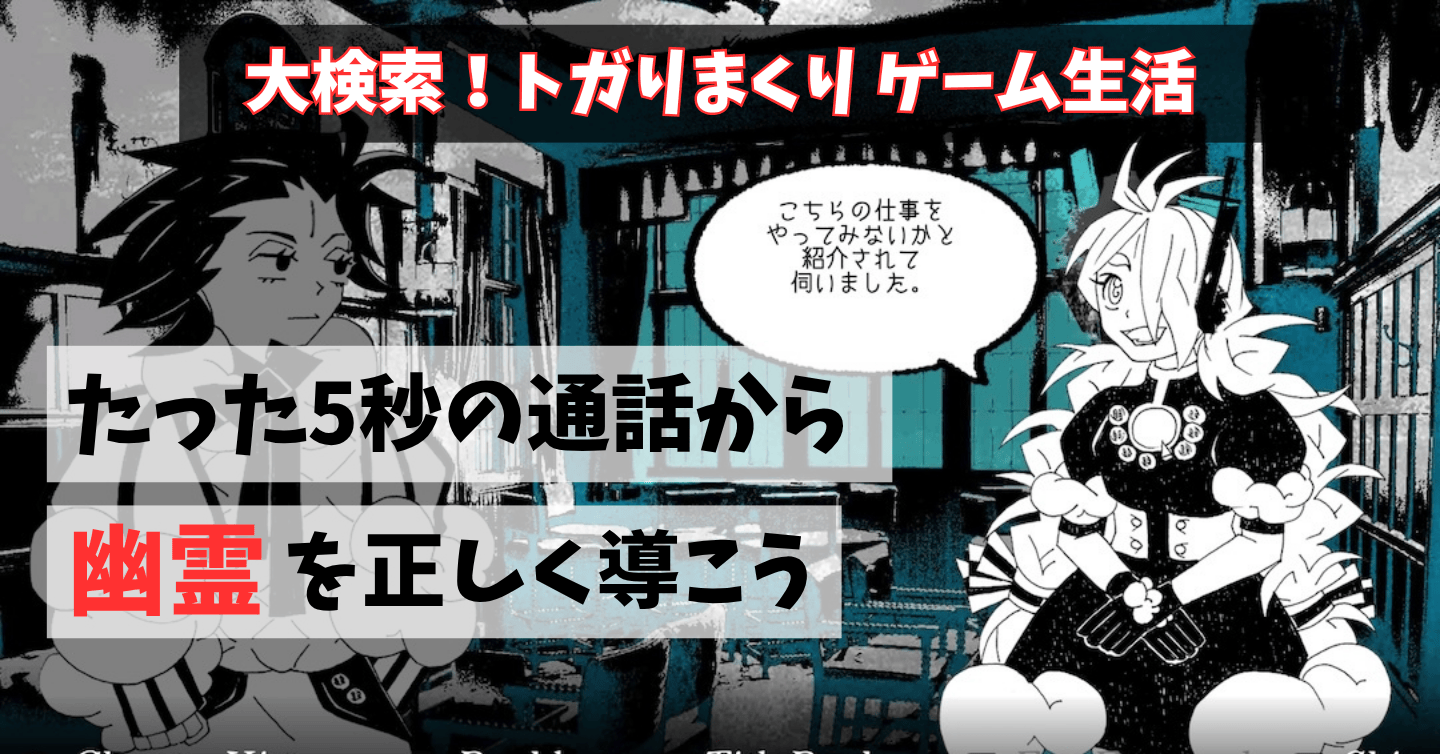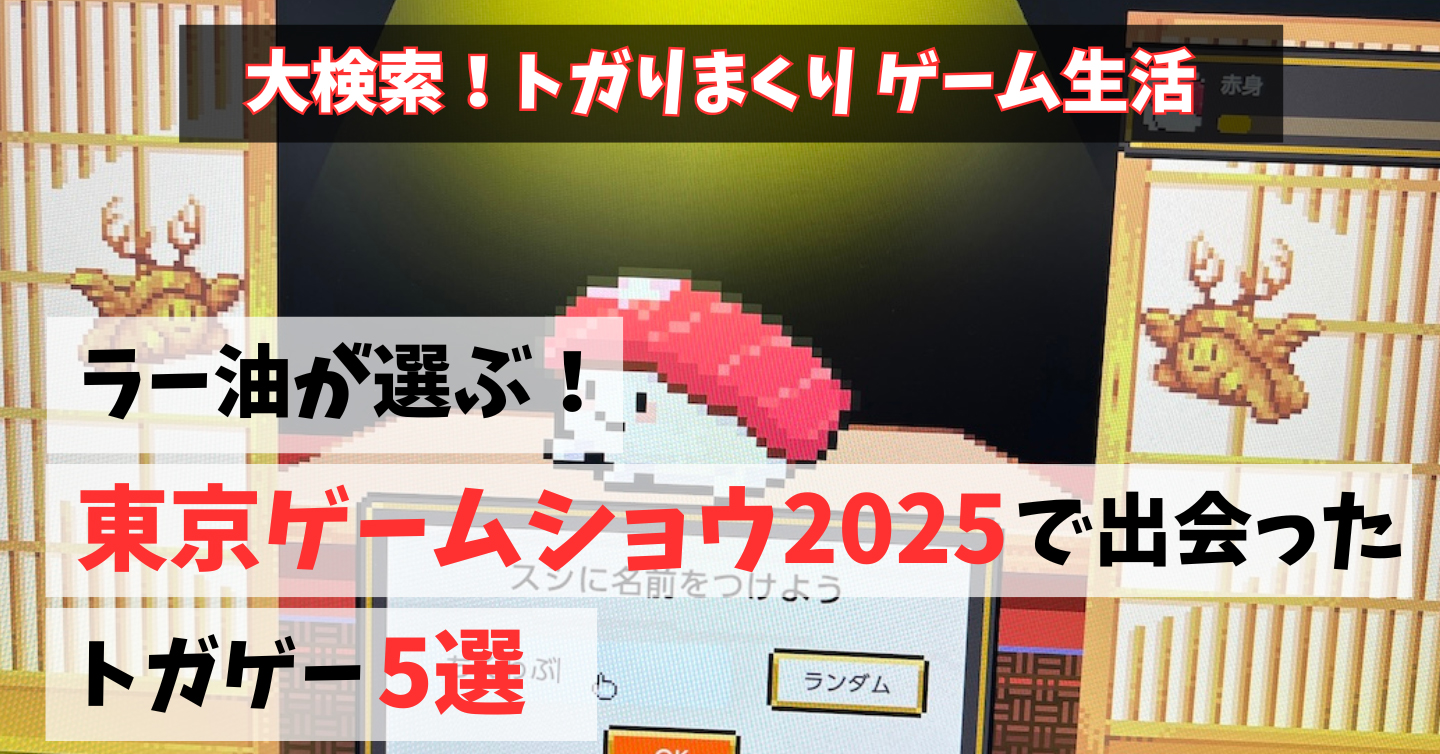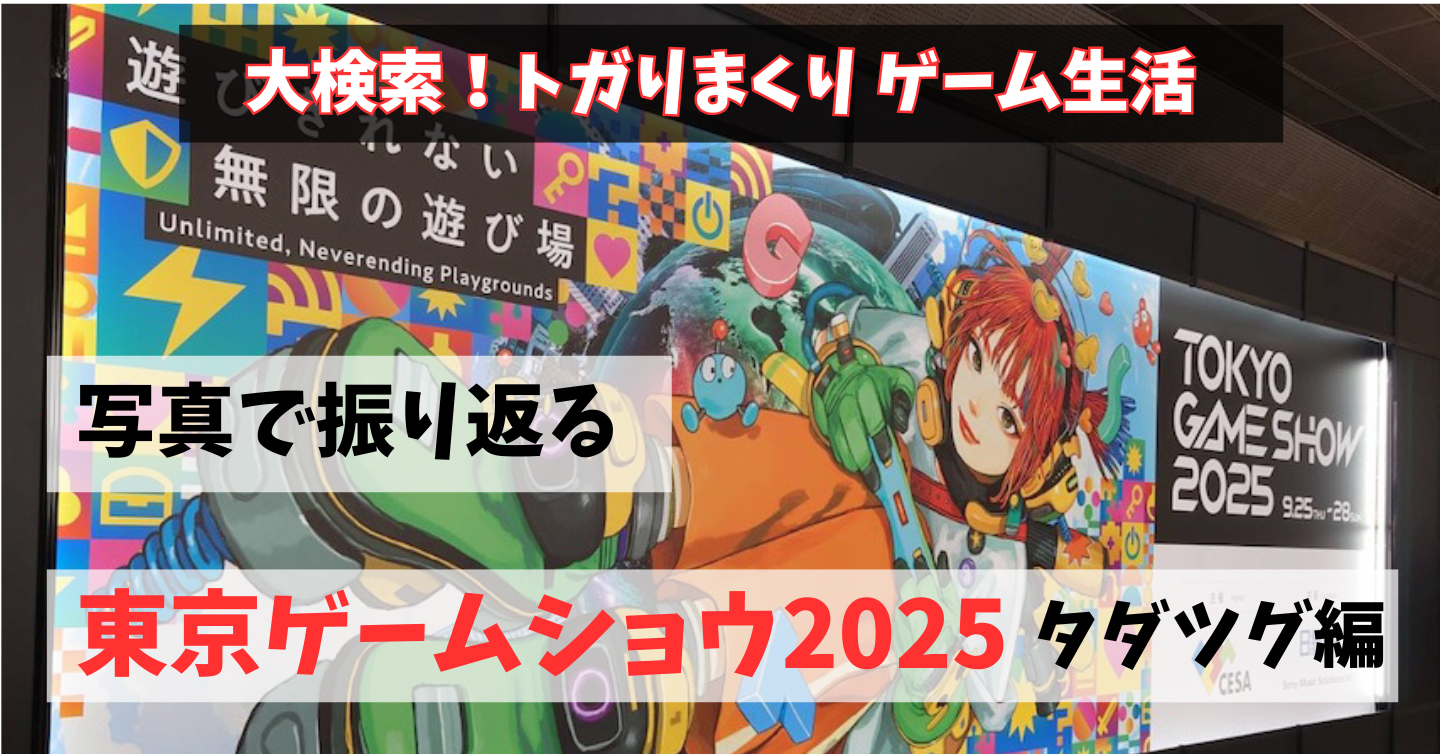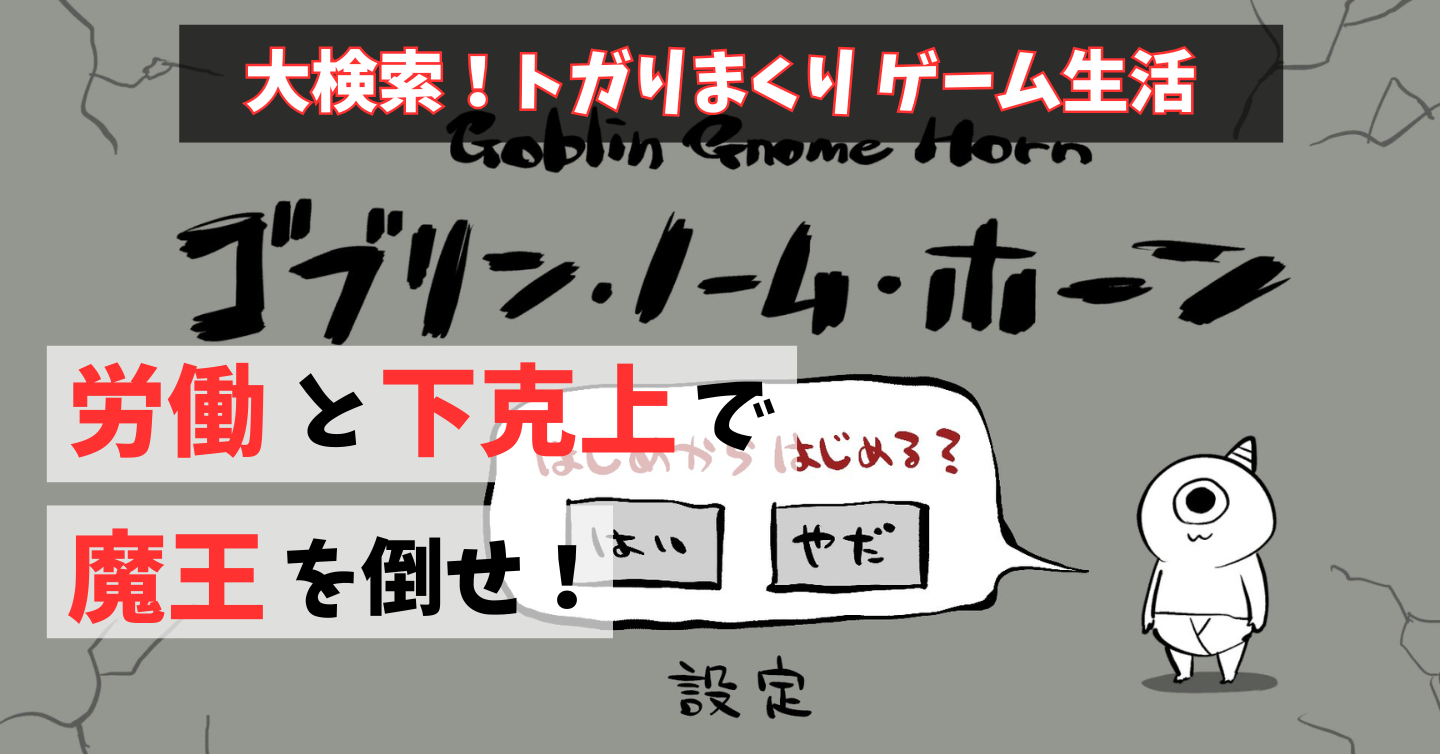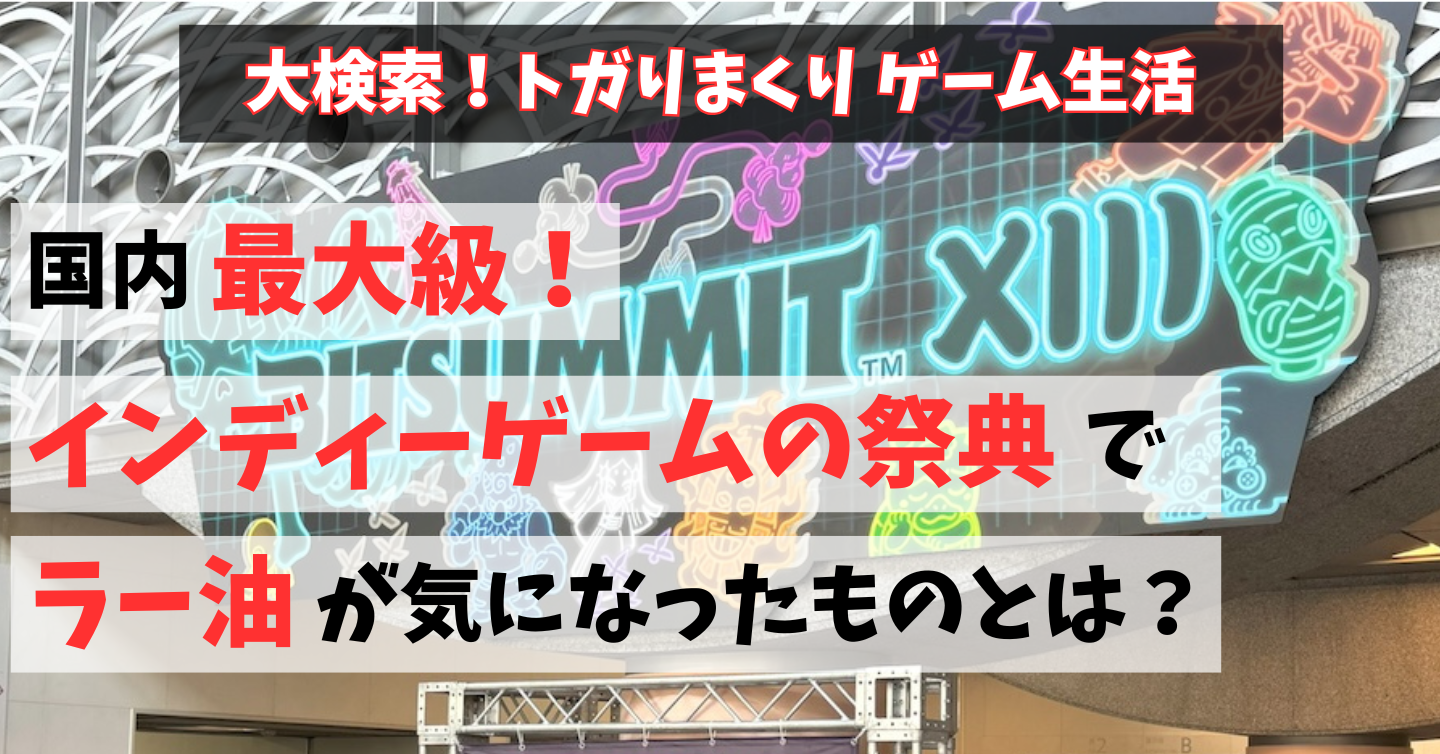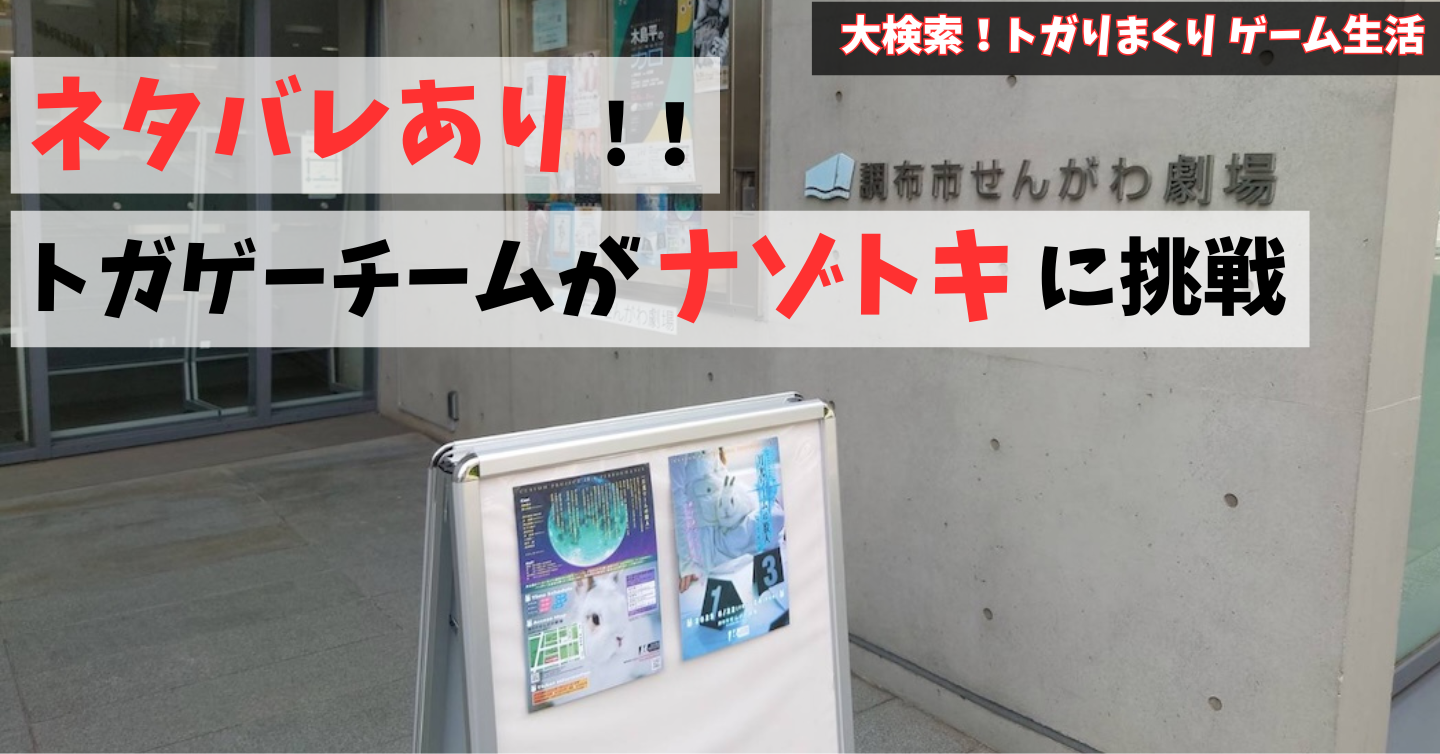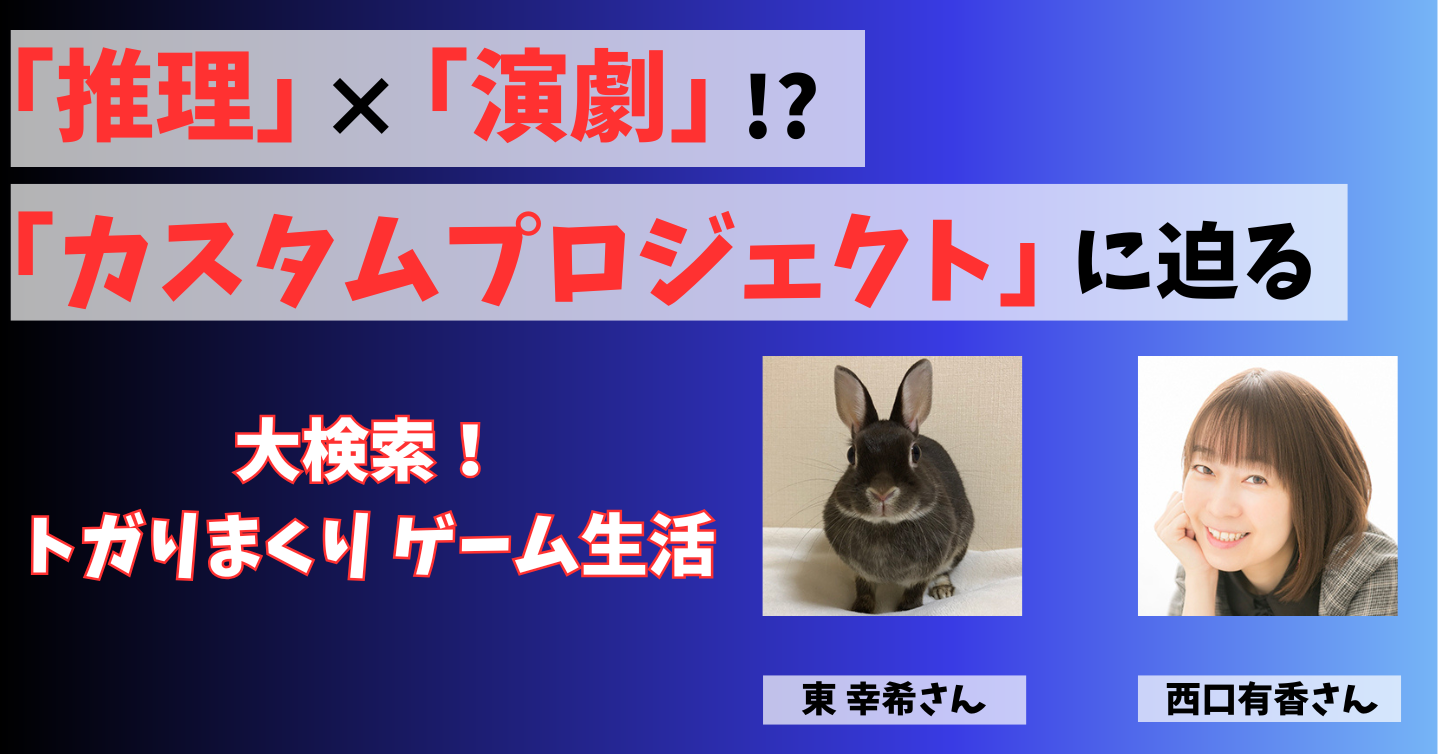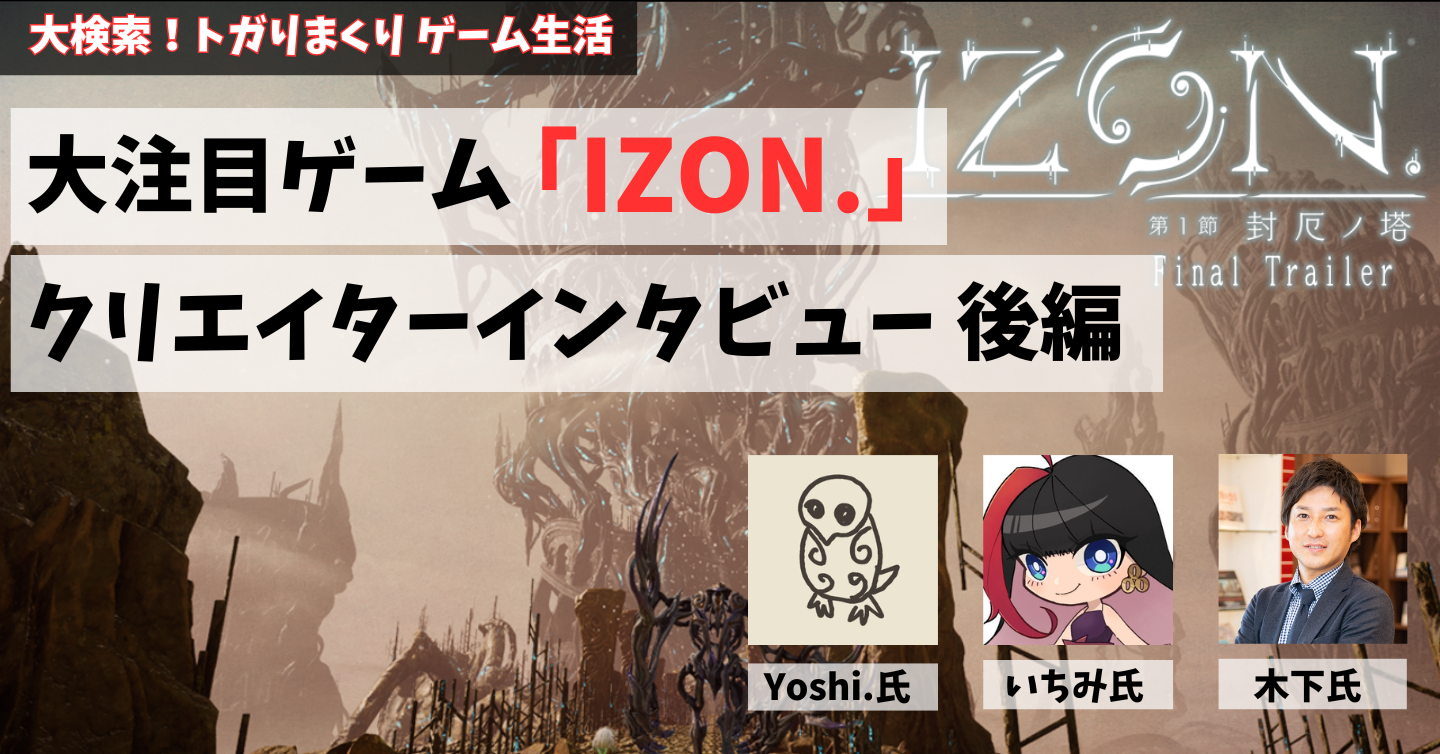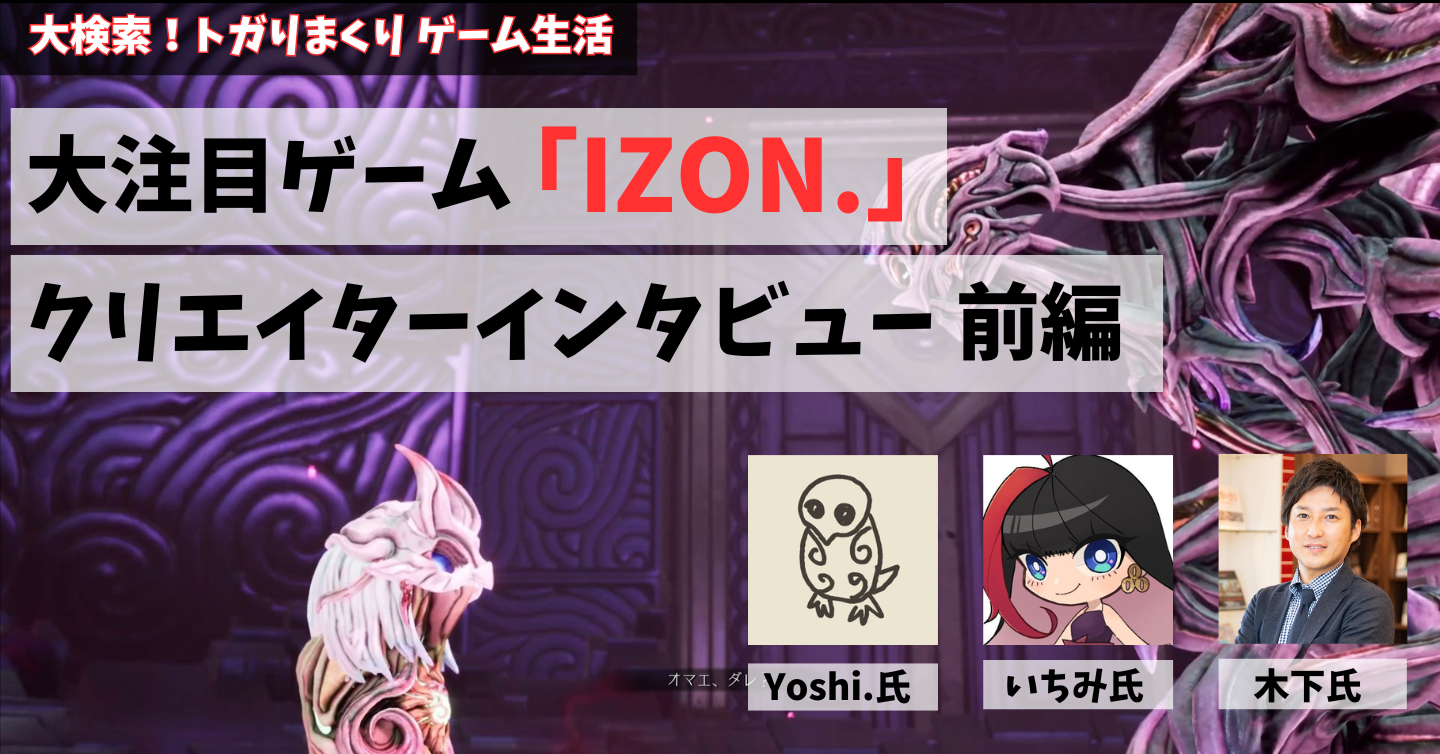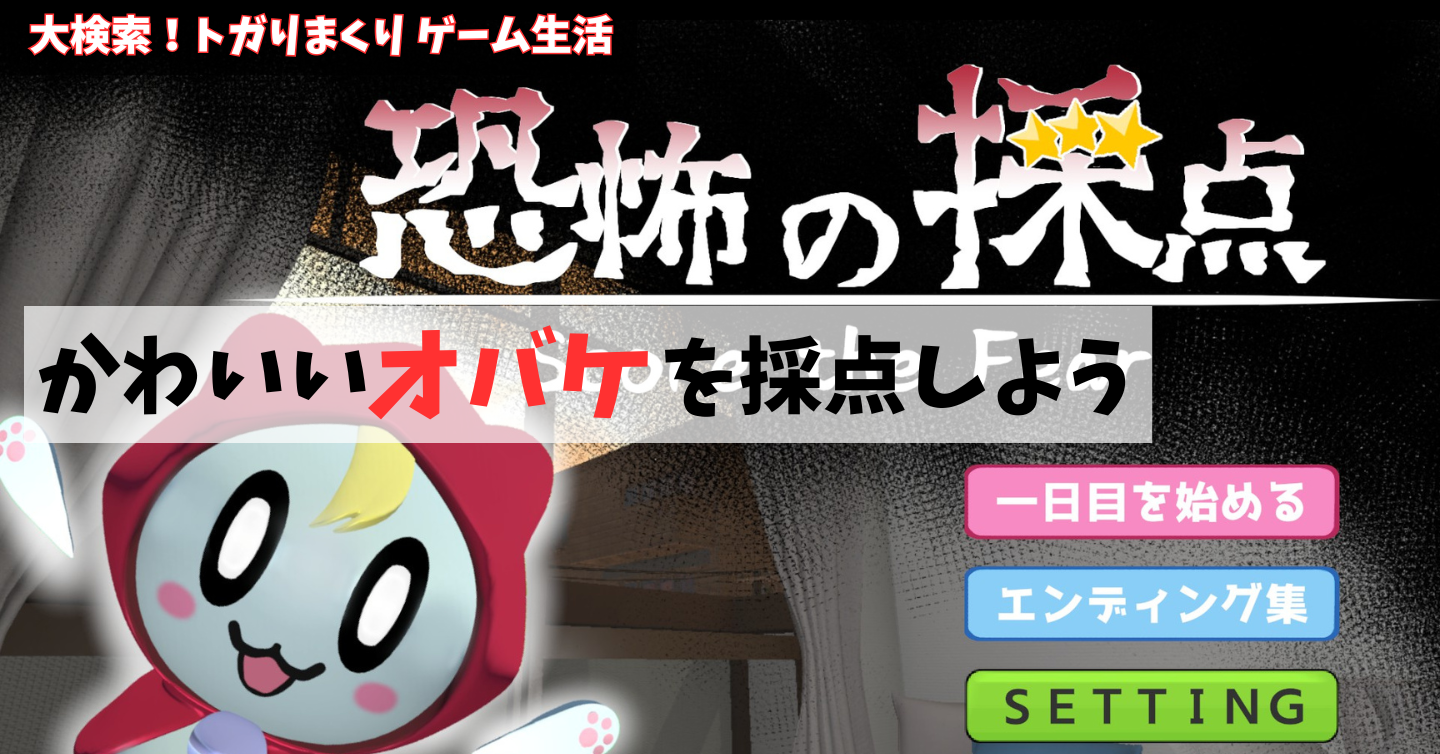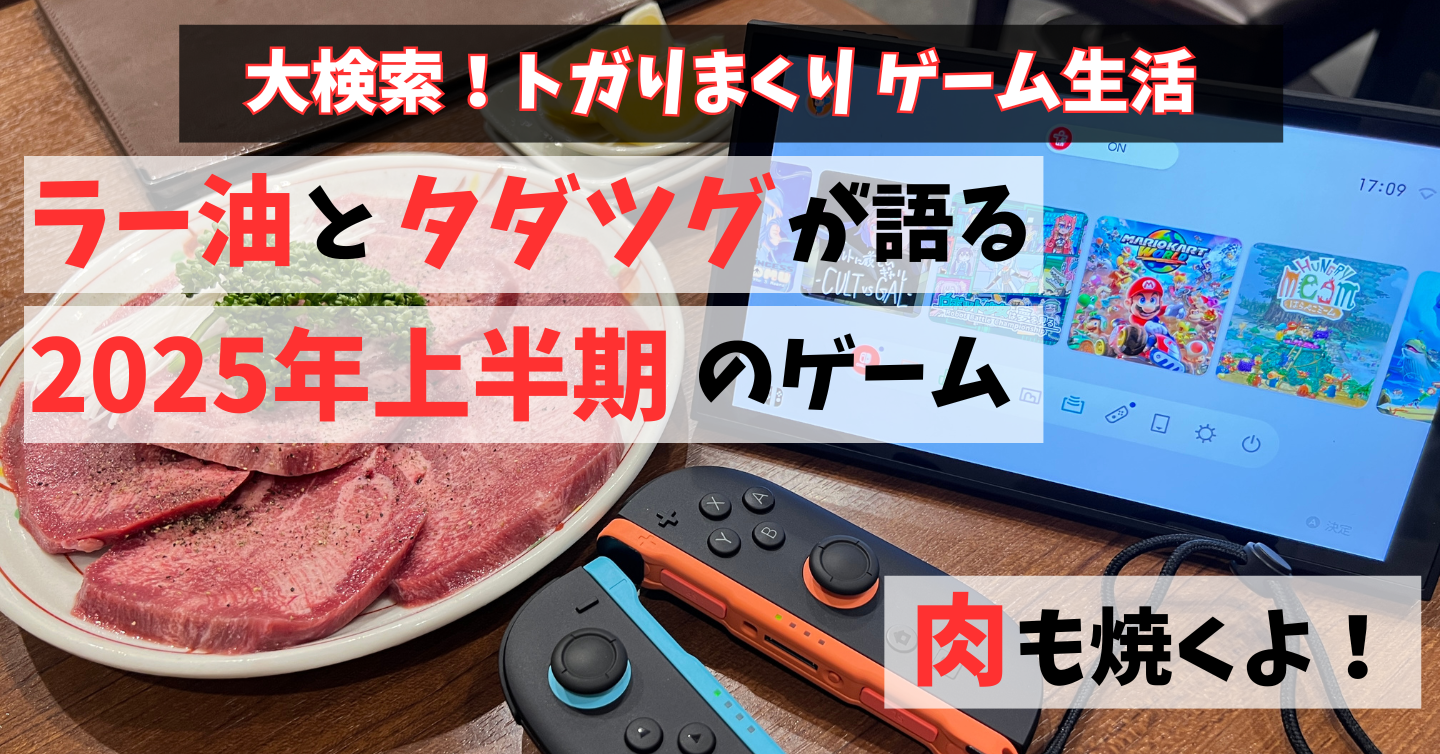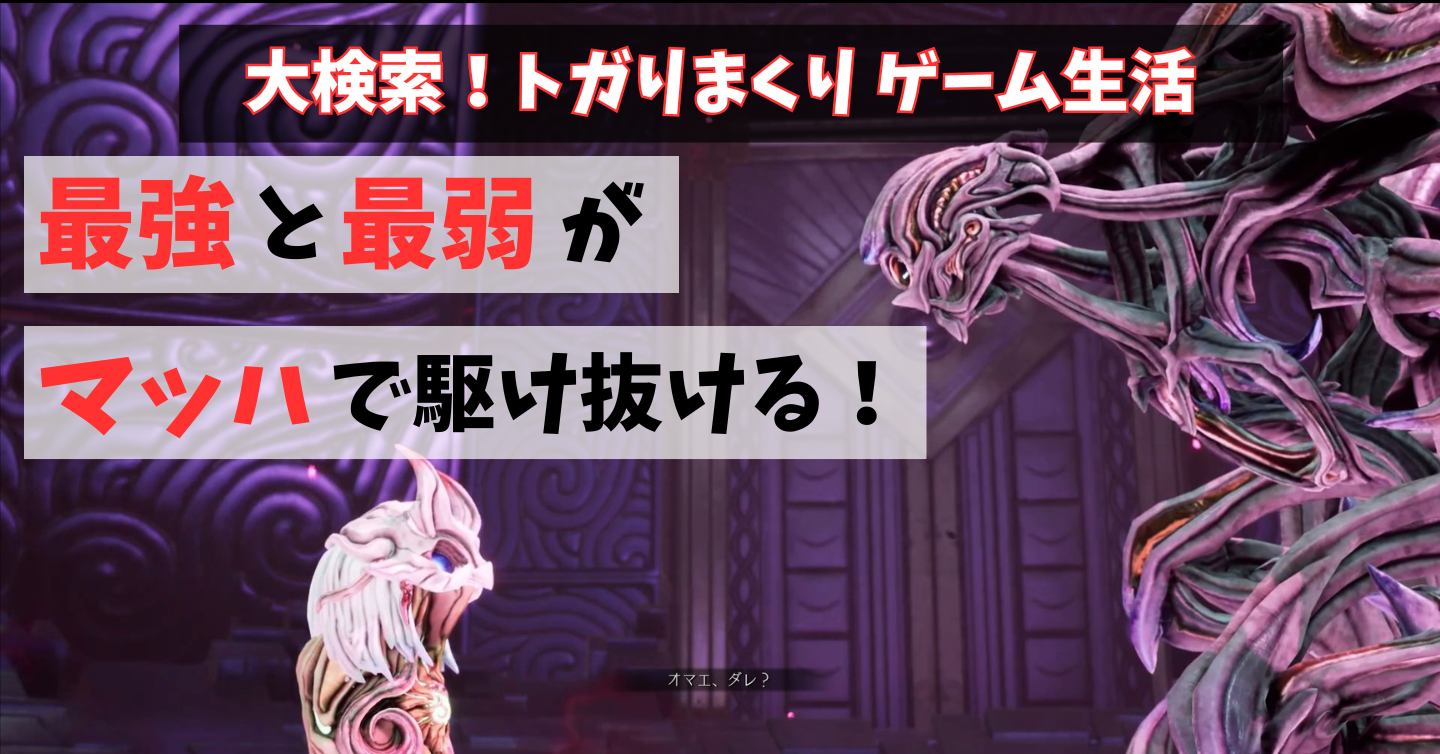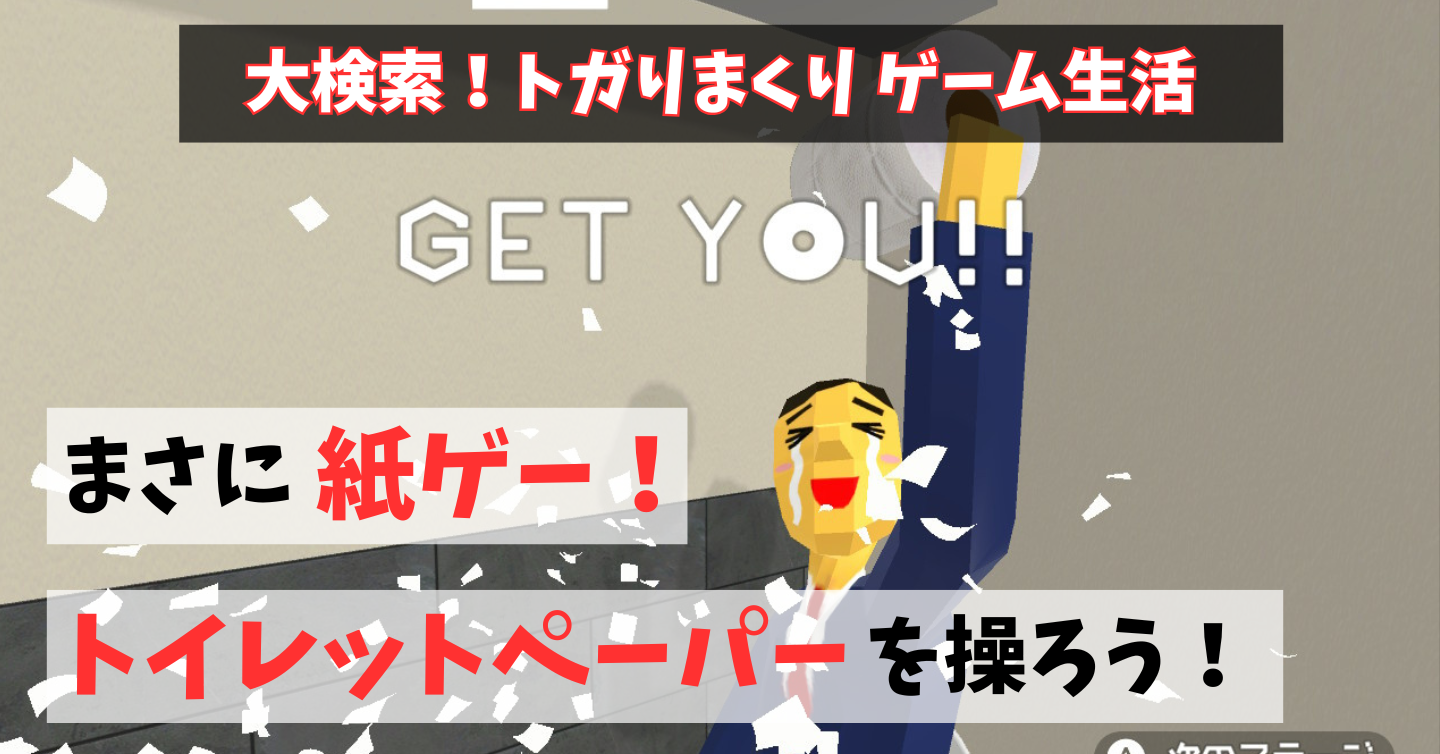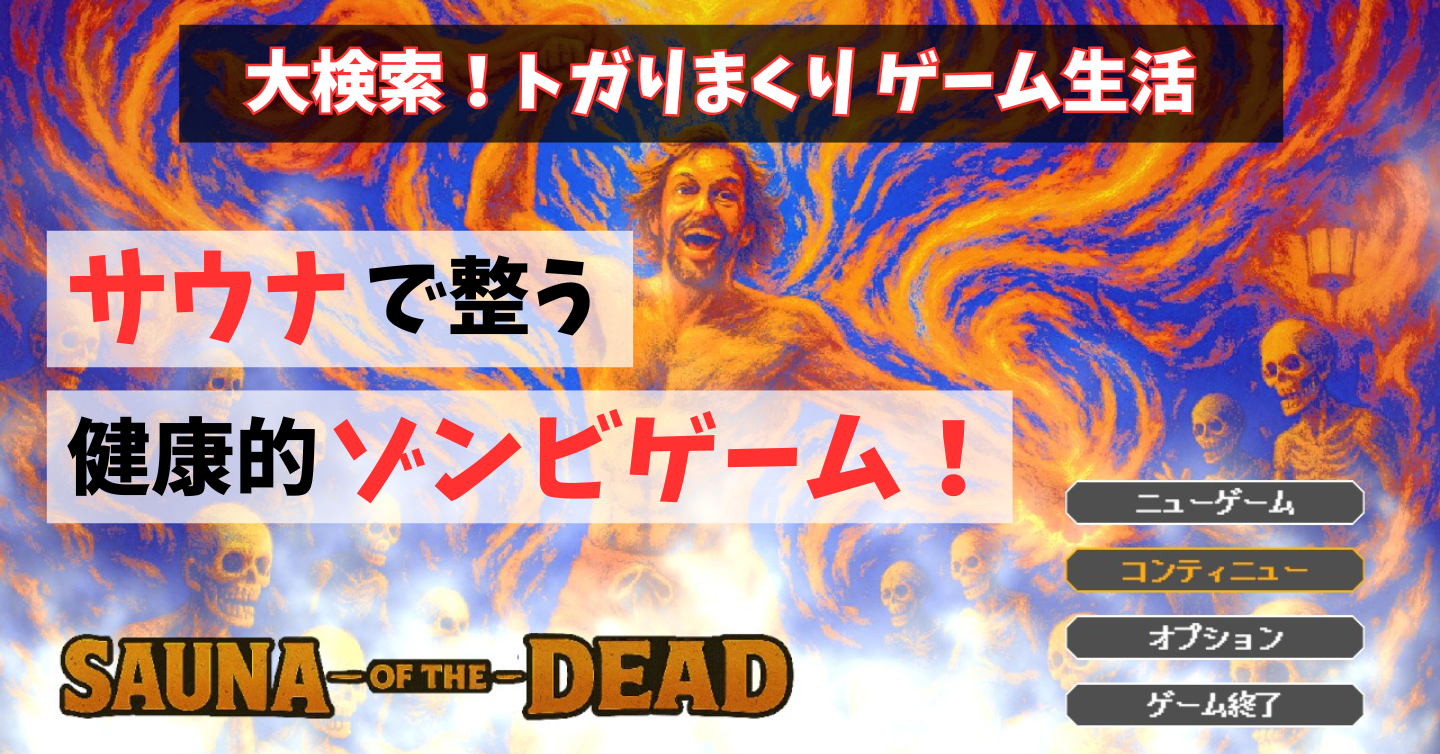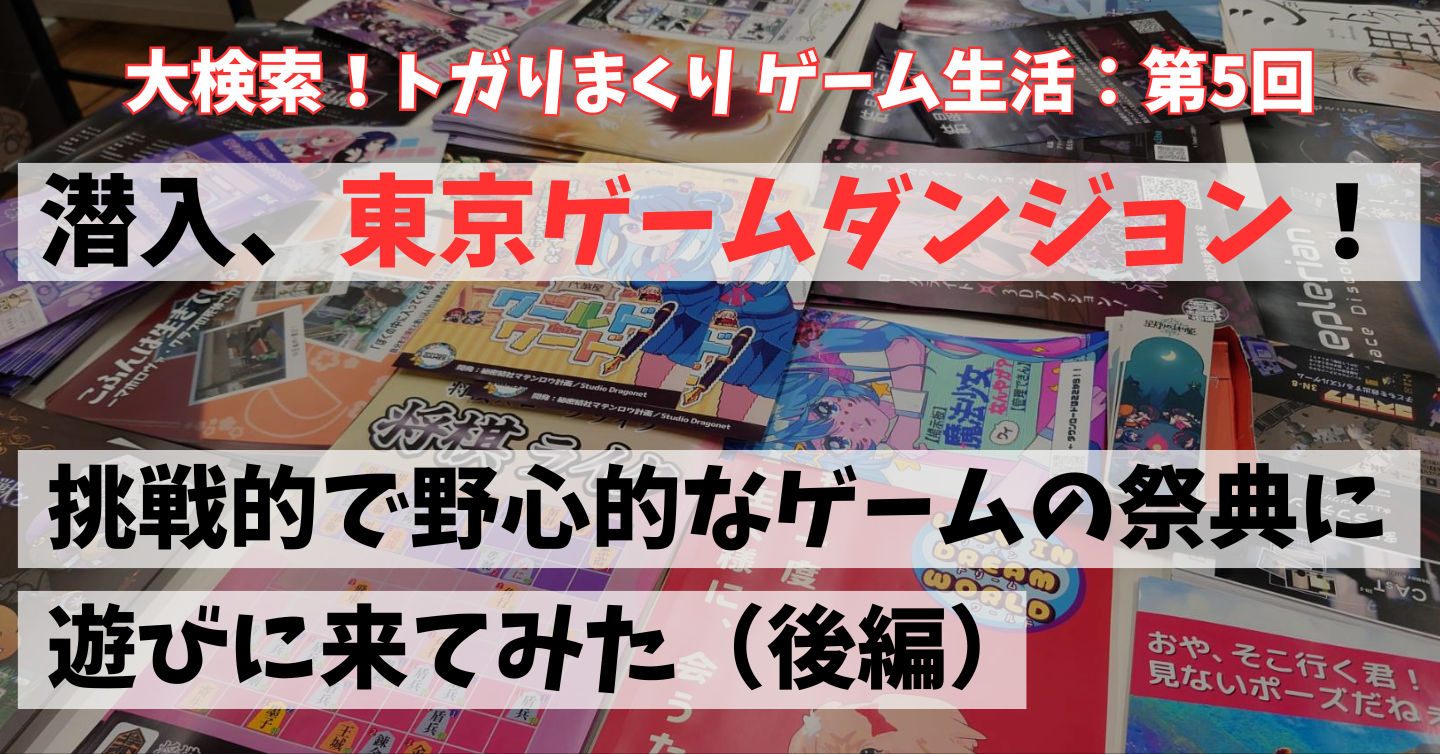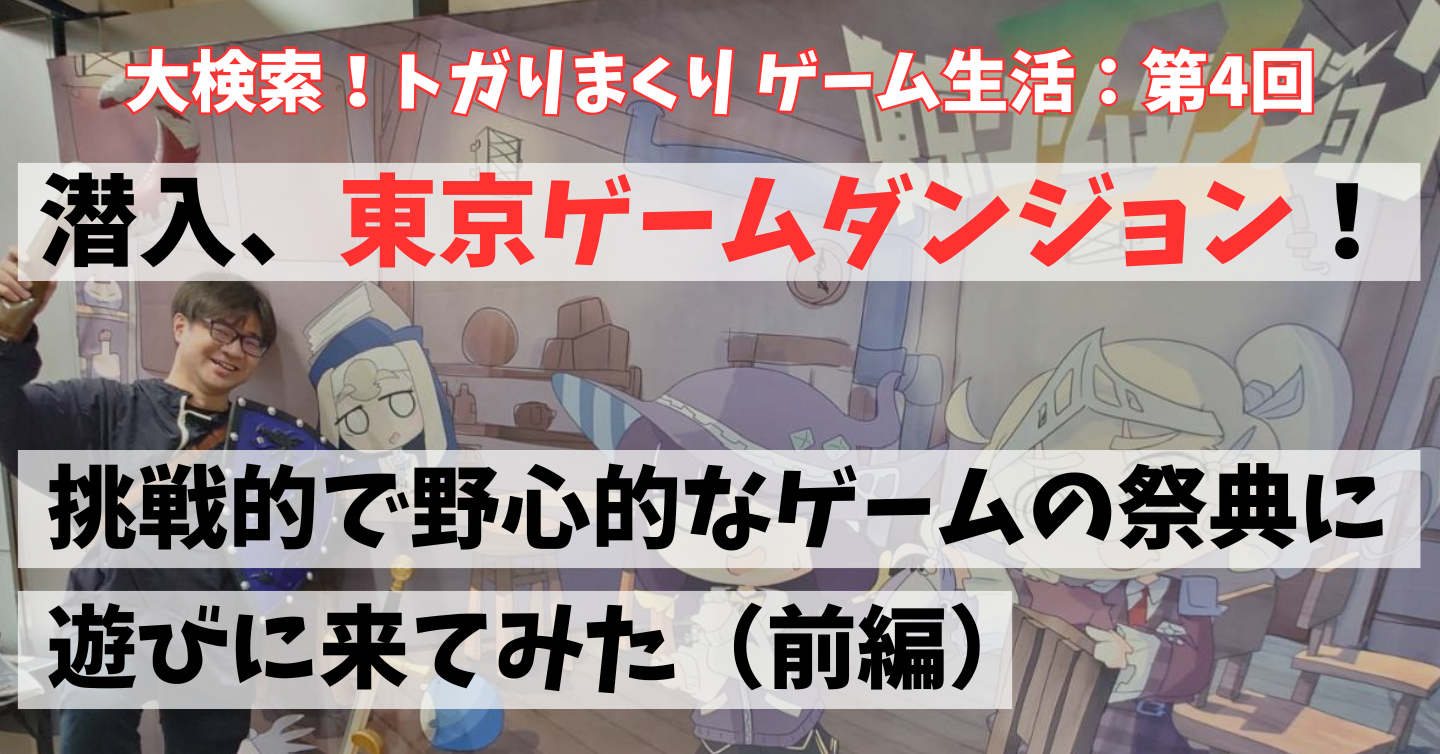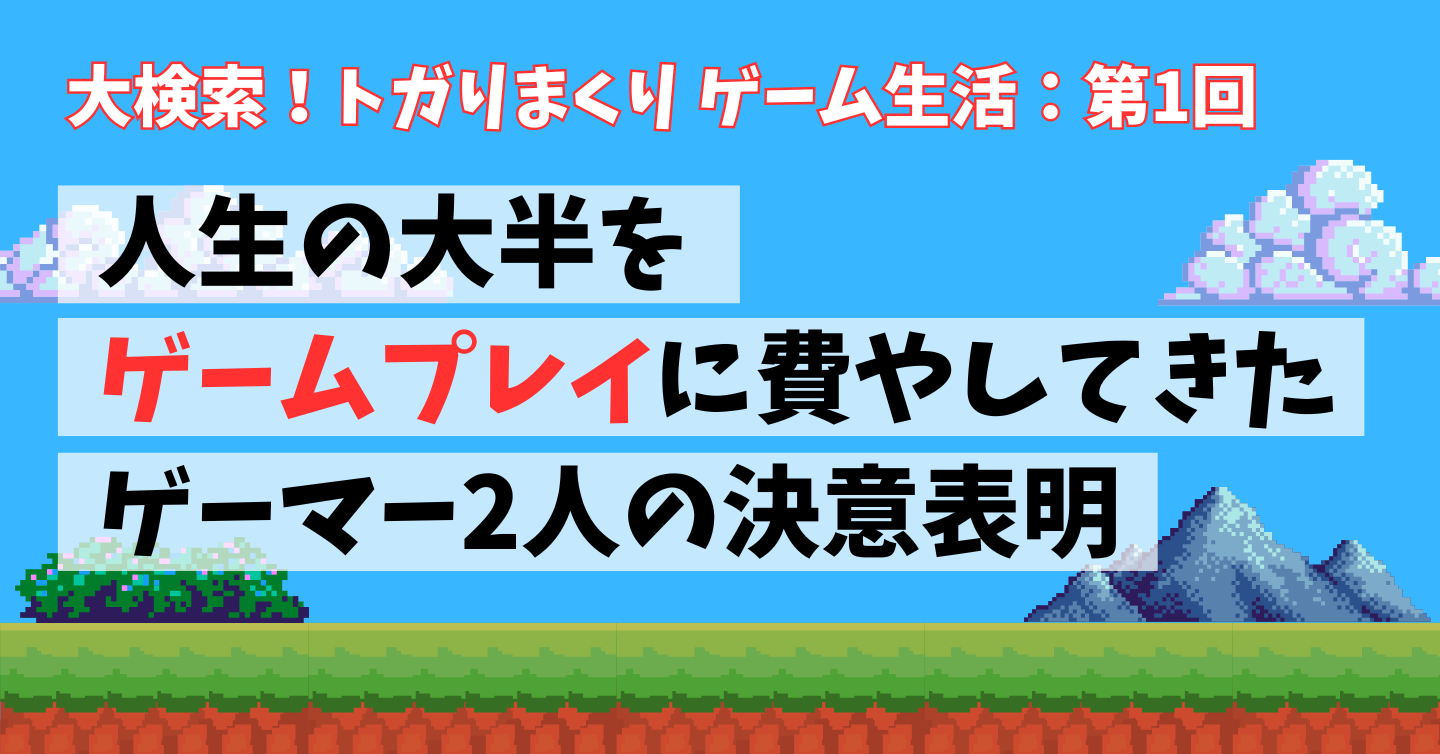ゆるく解説!これが「インディーゲーム」だ!
ゆるく解説!これが「インディーゲーム」だ!
知らないゲームを教えたい!(挨拶)
単独記事ではこれが初めて!ゲームブロガーの双葉ラー油です!
4月から始まった「大検索!トガりまくりゲーム生活」はインディーゲームを中心に、挑戦的な作品を紹介していくコーナーです。
しかし、そもそもインディーゲームとは何なのか?ここ数年でよく聞くようになった言葉ですよね。
「インディーゲームが面白い!」
「インディーゲームのイベントが大盛況!」
「インディーゲームのおかげで成績が上がりました!」
「インディーゲームのおかげで背が伸びました!」
「インディーゲームのおかげで彼女が出来ました!」
「裏の畑からインディーゲームがザックザク!」
みたいな。
3行目から雑にふざけてるので無視してください。いや、企業が参入して才能の取り合いになってる現状を考えると、裏の畑から採れたインディーゲームにみんなが群がる状況ではあるのか?

「大検索!トガりまくりゲーム生活」をする前に、一度この言葉の解説をしようという趣旨の記事です。
ただ、定義も出自も非常に曖昧で、度々議論になっている言葉でもあります。
あくまでも自分の視点で、初心者向けにざっくりした内容であることはご留意ください。
もしクレームが多かった場合、しれっと記事タイトルを「わかった気になってんじゃねぇぞ!インディーゲームがなんなのか分からん……」などに変えて乗り切る予定です。
海外生まれの挑戦的なゲーム概念。あの「マイクラ」もインディーゲーム!
基本的には「個人製作、あるいは小規模の開発チームによる作品」のことを指す言葉で、海外から生まれた概念。
歴史を遡ると該当する作品は果てしなく増えていくのですが、「インディーゲーム」という単語と共に語られるようになったのは2000年代に入ってから。
2008年に発売された『Braid』というパズルアクションゲームの大ヒットがきっかけと言われています。
同年2008年にはマイクロソフトのゲーム機である『Xbox360』にて、個人製作者が自由にゲームを配信できる「Xbox LIVEインディーズゲーム」という場所が登場。単語として固まってきたのはやはりこの辺りですね。
そこからは『マインクラフト』『UNDERTALE』『Celeste』『テラリア』『Stardew Valley』などなど。数えきれないほどのヒット作が生まれて現代に至ります。
昔はゲームといえば企業が作り、ゲームショップや量販店でパッケージを買うものでしたが、
PC向けのダウンロード販売サイトが台頭し、任天堂やソニー、マイクロソフトのゲーム機でもダウンロード販売が当たり前になったりと、販路の拡大に合わせてインディーゲームも発展したという流れです。
今では個人製作のゲームでも、ゲーム機で当たり前に遊べるので時代は変わった!
ちなみに「同人ゲーム」と「インディーゲーム」の違いですが……。
「国内発祥で主に同人イベントで趣味的に発表されるものが同人ゲーム」
「海外発祥で商業志向が強いものがインディーゲーム」
くらいの違いでしょうか。
ここもかなり定義が難しく、記事タイトルをこれ以上おかしくしたくないのでこの辺にしておきましょう。
「同人誌」と「ZINE」の関係に近いと言えるかもしれないですね。
だからこれ以上記事タイトルを危うくすることはやめろって!
多数の企業がインディークリエイターの支援に参戦。あの集英社に講談社も!
インディーゲームの盛り上がりに合わせて、企業がパブリッシングに乗り出す流れも加速しました。
多数の企業が、才能あふれるクリエイターに目を付ける戦国時代の始まり!
日本国内だと2011年に誕生した「PLAYISM」が有名なところで、ここ数年の新興レーベルだと「わくわくゲームズ」辺りが個人的に注目ですね。
集英社や講談社といった大手出版社もインディーゲームに参入。ノウハウを活かしてインディークリエイターをバックアップし、着実に成果を上げています。

集英社ゲームズは今年2月に発売した『都市伝説解体センター』が10日で10万本の大ヒット!
タイトル通り都市伝説を題材にしたアドベンチャーゲームで、見事なストリーテーリングと演出が特徴です。
小規模開発チームである墓場文庫が手掛けていますが、集英社側のアドバイスでブラッシュアップされた点も多いとのこと。『りぼん』でコミカライズ連載をしたり、発売直後から書店を巻き込んだイベントを開催したりと、販促面でも力が入っていました
講談社ゲームクリエイターズラボからは『違う冬の僕ら』が60万本を超えるヒット。
個人開発者であるところにょり氏の作品ですが、なんと2人プレイ専用のパズルゲーム。お互いに見えている世界が違うという構造が尖った1本です。
こちらは講談社繋がりで、メインビジュアルを『さよなら絶望先生』などの作者である、久米田康治氏が担当していました。
結局「インディーゲーム」って何?現状とそこに込めた意気込み。
ざっくりまとめてしまうと、現代においては「主流から外れた個性に溢れたゲームは、プロアマ問わずなんでもインディーゲーム」くらいの風潮ですね。企業が「社内インディー」と称して低コストの新作を発表したり、新人研修にインディーゲームを作らせるといった逆転現象も起こっています。
言葉として広がり過ぎてしまったので、こうなるのも止む無し。
ただ、こうなっていくと結局は宣伝力や発信力が無い、本当に小規模な作品が割を食ってしまうところ。
自分としてはそういう作品にもどんどんスポットを当てていきたいと考えています。
というわけで、そういう作品もしっかり取り上げていく「大検索!トガりまくりゲーム生活」をよろしくお願いします!
ライター紹介

双葉ラー油
老舗ゲームブログ『絶対SIMPLE主義』を20年以上運営するブロガー。「知らないゲームを教えたい!」をスローガンに、大作からニッチな作品まで取り扱う。特撮関連の造詣も深い。謎のマスクを被っているが別にプロレスラーではない。